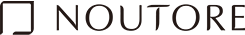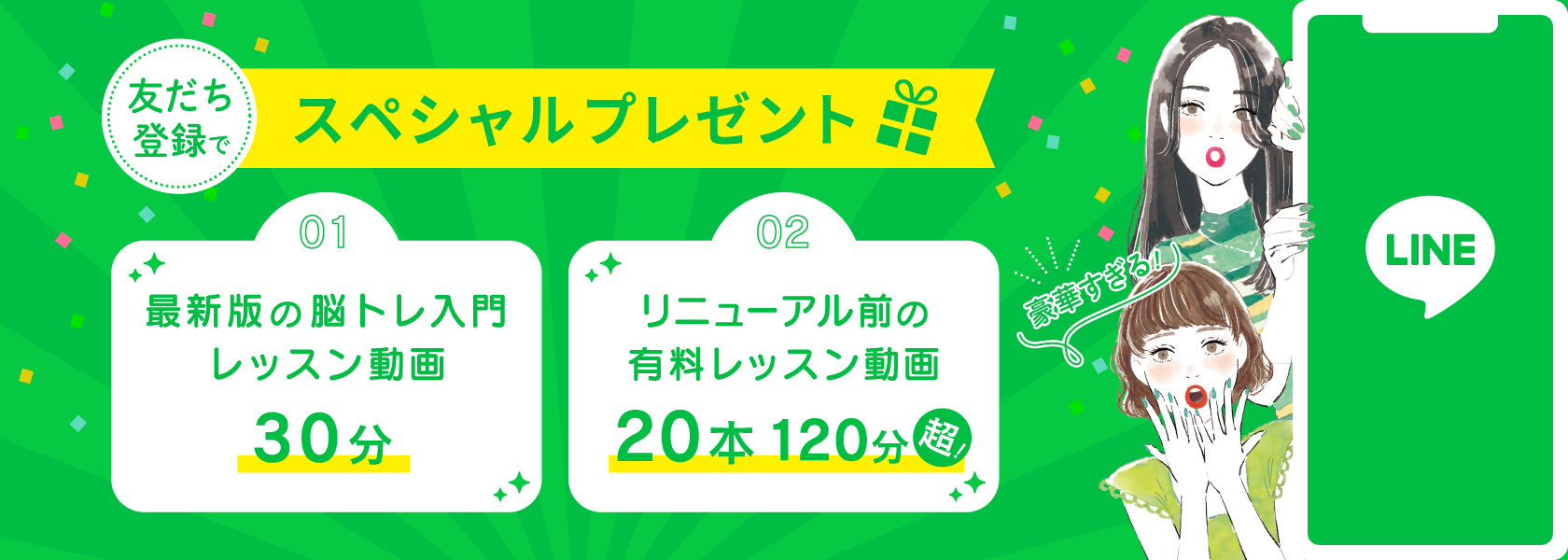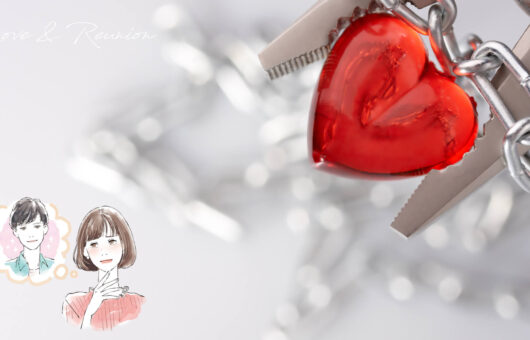人を信用できない。
そう思うと、社会生活のどこかでつまずきを感じやすくなります。
友達と仲良く暮らしたい、気持ちよく仕事をしたい、結婚やパートナーシップのように深い関係を築きたい。
その願いがあっても、「信じられない」という壁の前で立ち止まってしまう。
本当は誰かと一緒に安心を分かち合いたいのに、疑いが先に出てしまうことで、心の距離は縮まらず、孤独感が募っていく――そんな苦しさを抱えている人は少なくありません。
Contents
信用できない状態の正体|人間のデフォルトは「委ねる」
いま、あなたは人を信用できない状態にあるかもしれません。
けれど、生まれたその瞬間から誰かを信用できなかったわけではないはずです。
生まれたばかりの頃の私たちは、判断も選択もできないまま、ただ泣き、ただ委ね、ただ守られてきました。
つまり人間の最初の姿、デフォルトの姿勢としては「信じるかどうか」を考える以前に、すでに他者に委ねて生きている存在なのです。
そして、成長する過程で何かしら安心が壊れる出来事を通して「人を信用しない」と無意識で選んだ瞬間があったはずです。
本来は「信じないと決めた」という一つの選択(I choose not to trust)にすぎなかったものが、繰り返しの積み重ねによって「信じられない」(I can’t trust)という状態に変わっていきます。
だからこそ、戻りたい力と戻れない壁のあいだで、私たちは長く揺れ続けるのです。
人を信用できない状態ができあがるプロセス
赤ん坊の頃の人を信用する、しない以前に“委ねる”のがデフォルトだった時代から、一足飛びに「人を信用できない今の状態」が出来上がったわけではありません。
そこには長い時間をかけて出来上がったプロセスがあるのです。
その理由も背景もわからないまま、ただ「人を信じよう」と思ってもうまくいかないのは当然のこと。
まずは、どうやって今の「信じられない」という状態がつくられてきたのかを、ひとつずつほどいていきましょう。
1. 生存本能(警戒)
最初にあるのは、本能としての警戒心です。
生き延びるために備わったセンサーで、危険の匂いを察知して身を守ろうとする働き。
これは悪いものではありません。むしろ必要な力です。
けれど、人生のどこかで――人に完全に委ね切っていたときに、その安全が脅かされる経験をした瞬間があったのでしょう。
当時のあなたは無意識に「人に100%委ねるのは危ないのかもしれない」と判断したのです。
その記憶が生存本能の奥に刻まれることで、安心できる相手に対しても「もしかしたら敵かもしれない」と感じやすくなり、ここから歯車が少しずつ狂い始めます。
2. 学習(裏切り体験・環境・親の影響)
生存本能が「人に委ねるのは危ないのかもしれない」と反応したあと、次に重なっていくのは具体的な体験です。
- 信じていた人からの裏切り
- 家庭の中の不安定さ
- 親の過干渉や放置
- 学校や職場での人間関係のトラブル
こうした出来事が繰り返されると
やっぱり人に委ねると傷つく
という確信めいた学習が心に刻まれていきます。
本来なら一度きりで終わるはずの警戒反応が、「証拠集め」をするように積み重ねられていき、やがて「人は信用できない」という回路そのものが強化されていくのです。
さらに厄介なのは、子ども時代の学習ほど深く刷り込まれやすいということ。
善悪や適切さをまだ自分で判断できない時期に
人は危険だ!
と感じさせる出来事が繰り返されると、それは単なる経験を超えて“世界の前提”として固定化されてしまいます。
こうして「危険を察知した本能」と「危険を確信させる学習」が結びつき、次の思い込みの段階へとつながっていきます。
3. 思い込み(人は危険だという信念)
体験の積み重ねは、やがて「思い込み」へと形を変えていきます。
- 人は裏切るもの
- 近づけば損をする
- 油断してはいけない
そんな信念が、心の奥に静かに固まっていくのです。
この思い込みは、自分を守るための鎧のような役割を果たします。
しかし、その鎧が厚くなりすぎると、差し伸べられた手さえ拒んでしまう。
本当は温かさを求めているのに、自分自身でその入り口を閉ざしてしまうのです。
さらに思い込みは、日常の言葉にも表れてきます。
私が運営している脳トレカレッジ(自己対話の学校)でメンバーと話していると、過去の体験から思い込みが強くなっている人ほど
嘘をつかれたんです!
という言葉をよく使う傾向があります。
相手がただ情報を間違えていただけでも、「嘘をつかれた」と受け取ってしまう。
これはその人が特別に騙されやすいからではなく、「人は裏切るもの」という信念が強く働いているからです。
このように、思い込みはただ心の奥に潜んでいるだけではなく、言葉や解釈のフィルターとして日常に染み出し、さらに「やっぱり人は信用できない」という証拠を自分で積み重ねてしまうのです。
4. 習慣化(信じないという自動反応)
そして最後に、それらは習慣として定着していきます。
相手を疑う、試す、先に距離を置く――そんな反応が、考えるより先に自動的に立ち上がるのです。
その態度に触れた相手の心は冷え、関係はさらに遠のき、「やはり人は信用できない」という“証拠”が積み上がっていきます。
こうして過去の学習と信念が何度も補強されるうちに、もはや「I choose not to trust(信じないと選んでいる)」ではなく、「I can’t trust(信じられない)」という固定化した状態に変わってしまうのです。
本来は一度の選択にすぎなかったものが、長い時間をかけて自動反応へと変質していく――この移行こそが「人を信用できない」という悩みを深くしている要因なのです。
こうして「1→2→3→4」と積み上がったものだからこそ、克服するときには逆順でほどいていく必要があります。
いきなり「人を信じてみよう」とするのではなく、まずは無意識の反応を観察し、そこから少しずつ“信じる”回路を取り戻していく。 これが、戻るための道筋です。
なぜ悩みになるのか?(生存本能と社会本能のねじれ)
人を信じないと決めること自体は、一つの選択です。
信じると危険だからやめておこう
という判断は、生存を守るための個人レベルの選択として理解できます。短期的に見れば、自分を傷つけないための合理的な行動なのです。
けれど、それだけで済まないのは、この問題が「個人の選択」と「人間に備わった根源的な本能」との衝突だからです。
一つは、怖いから守りたいという生存本能。
これは「自分を守るためには信じない方がいい」とその都度判断する、個人の選択としての本能です。
もう一つは、つながりたい・分かち合いたいという社会本能。
これは誰もが人間として最初から備えている、根源的な欲求なのです。
この二つがねじれることで、私たちは
信じたくないのに、つながりたい
怖いのに、求めてしまう
という相反する力に引き裂かれます。
まるで、個人が選んでインストールしたアプリと、機器そのものに組み込まれたOSの相性が合わず、全体の動作に不具合が出るようなものです。
この不調和こそが、「人を信用できない」が単なる選択の問題ではなく、深刻な悩みとして現れる理由なのです。
信用できないことで起こる影響
「人を信用できない」というのは心の中の問題にとどまらず、日常の関係や未来の可能性にまで影響します。
とくに恋愛や仕事の場面では、その影響がわかりやすく表れやすいのです。
恋愛への影響
恋愛は「信じる・委ねる」という要素が強く求められる関係です。
そこに「信用できない」が入り込むと、次のような悪循環が起こりやすくなります。
- 相手を疑い続ける不安ループ
- 相手を束縛し、自由を制限しようとする
- 相手の周囲への嫉妬が止まらない
本来なら心を支えてくれるはずの恋愛関係が、不安と緊張の戦いの場に変わってしまうのです。
仕事への影響
仕事ではチームや同僚との協力が欠かせません。
しかし人を信用できないと、次のような壁が立ち上がります。
- 任せられずに自分一人で抱え込む
- 同僚や部下の言葉を疑い、ぎくしゃくした関係になる
- 上司や顧客への不信感が強まり、成果や評価に響く
信頼を土台にするはずの職場で孤立感が深まり、キャリア全体に影響を及ぼすこともあります。
このように、信用できないことは「内面の苦しさ」だけではなく、恋愛や仕事という具体的な生活領域で実害を生み出します。
だからこそ、多くの人が「どうにかしたい」と本気で悩むのです。
人を信用できない状態をほどいていく4つのステップ
「人を信用できない」という状態は、①生存本能 → ②学習 → ③思い込み → ④習慣化の順で積み重なってきました。
つまり克服のときは、その逆順でほどいていく必要があります。
ここから紹介する4つのステップは、いまの自動反応をゆっくり緩め、再び“信じる力”へ戻っていくための道筋です。
ステップ1:習慣をゆるめる
まずは無意識に繰り返している「疑う・試す・距離を置く」といった反応に気づくことから始めます。
いきなり信じようとせず、小さな実験を重ねてみるのです。
この人のこの部分だけは信じてみよう
と部分的に委ねる。
そうした小さな成功体験が、習慣の硬直を少しずつほぐしていきます。
ステップ2:思い込みを見直す
次に、自分の中にある「人は危険だ」「裏切られるに違いない」といった信念を言葉にしてみましょう。
曖昧な不安が言語化されるだけで、思い込みの輪郭が見えてきます。
そのうえで
裏切りとは具体的にどういうことなのか?
それが起きたら本当に生きていけないのか?
と問い直してみる。
裏切りの基準を明確にすることで、必要以上に怯えなくてもよい場面が増えていきます。
ステップ3:過去の体験を癒す
思い込みの根っこには、かつての裏切りや孤独の体験があります。
それをなかったことにするのではなく、
あのときは仕方がなかった。当時の自分はよくやっていた。
と自分自身に語りかけてみることが大切です。
過去の自分を責める代わりに労わることで、心に溜まっていた痛みが少しずつ和らぎます。
そのとき、学習として固まっていた「委ねる=危険」という結論が、少しずつ揺らぎ始めるのです。
ステップ4:生存本能の安全感を再構築する
最後に取り組むのは、一番深い層にある「怖いから守りたい」という本能の調整です。
安全な環境で安心を感じる経験を重ねること――これが回復の核心になります。
- 信頼できる小さなコミュニティに身を置く
- 体を休めて呼吸を整える
- 自然に触れて心を落ち着ける。
そうした体感的な安心が積み重なることで、生存本能そのものが「人とつながっても大丈夫」と再学習していきます。
この4つのステップは、いきなり劇的に変えるためのものではありません。
ただし少しずつ積み重ねることで、「I can’t trust(信じられない)」という固定化した状態が、「I choose to trust(信じてみるという選択)」へと戻っていく道が開けるのです。
よくある落とし穴|一点に全てを託してしまうこと
脳トレカレッジ(自己対話の学校)でご相談を伺っていると、よく見かけるパターンがあります。
それは
いままで誰も信じられなかったけれど、この人なら大丈夫
と感じた相手に、これまでの思いを一気に託してしまうケースです。
長いあいだ「本当は信じたかったのに信じられなかった」気持ちが蓄積しているため、そのたった一人に全てをかけてしまうのです。
すると、相手が例えばこんな小さなことをしただけでも「裏切られた」と強烈に感じてしまいます。
- 約束の時間に 1時間遅れて来た
- 100円など少額を借りっぱなしで忘れていた
- お願いしていたことをやってくれなかった
など、ほんの些細な出来事なのに、積み重なった
本当は信じたかったのに!
という気持ちに年数分の利息をつけて失望をぶつけてしまい、関係を壊してしまうことも少なくありません。
これは特別なケースではなく、現場で本当に頻繁に目にする現象です。
だからこそ「一点に全力投資」ではなく、小さく分けて信じる練習を重ねることが大切なのです。
まとめ|「信じる」を選び直す力は、今もあなたの中にある
人間の出発点は「委ねること」です。
生まれたばかりの頃の私たちは、判断も選択もできないまま、ただ周囲に身をゆだねて生き延びてきました。
そこからの成長のなかで、いつしか「信じない」という選択を無意識に重ねてきただけなのです。
大人になった今なら、その選択を意識的にやり直すことができます。
たとえ過去に「信じない」と決めてしまった自分と出会う必要があったり、心の痛みを思い出したりする場面があったとしても――もう一度「信じる」を選び直すことは可能です。
そもそもの私たちのOSは「信じる」「委ねる」に設定されています。
一度初期化するように立ち戻れば、誰かにまっすぐ委ねる感覚を、少しずつ取り戻していけます。
焦らなくても大丈夫。
静かに、自分の内側に戻るようにして――「信じる」を選び直す力は、今もあなたの中に生きています。
📝次に読みたいオススメ記事
①彼氏を信じられない…その奥にある“自分への不信感”と向き合うには?
②自己信頼感とは?──“自分を信じる”という言葉の中身をひも解く