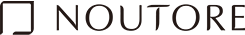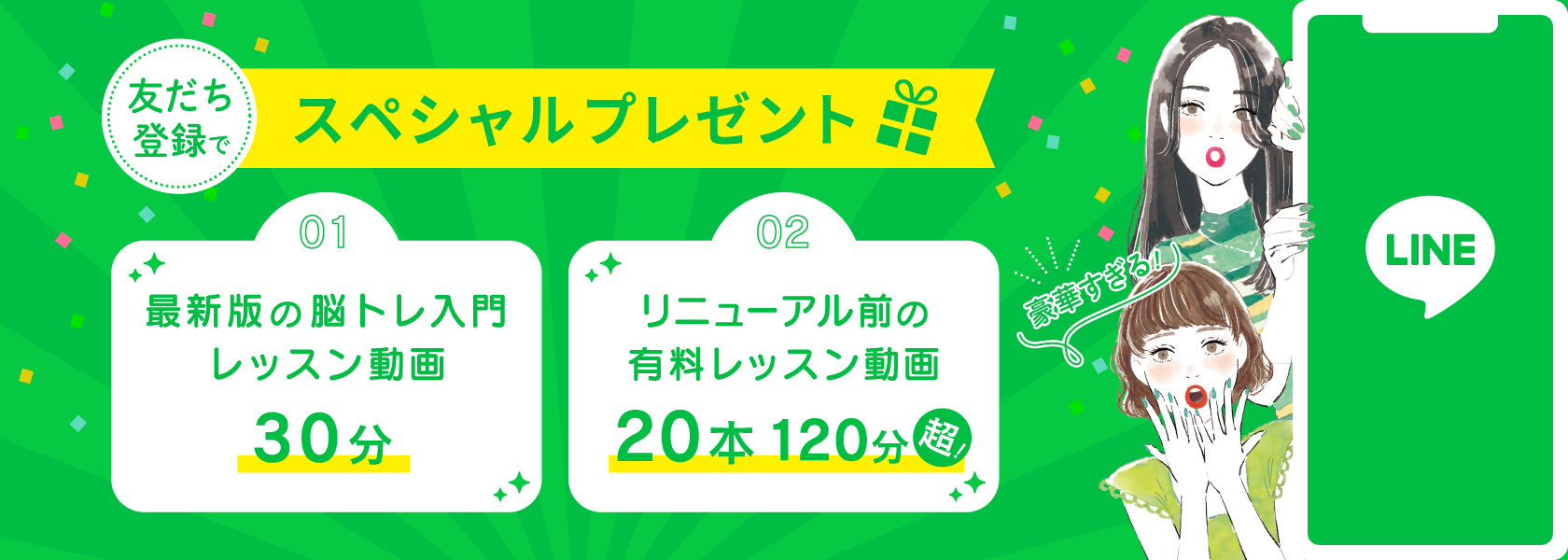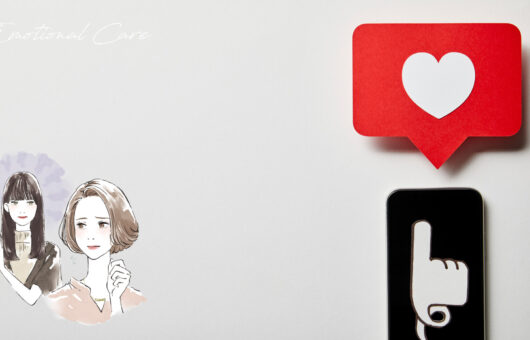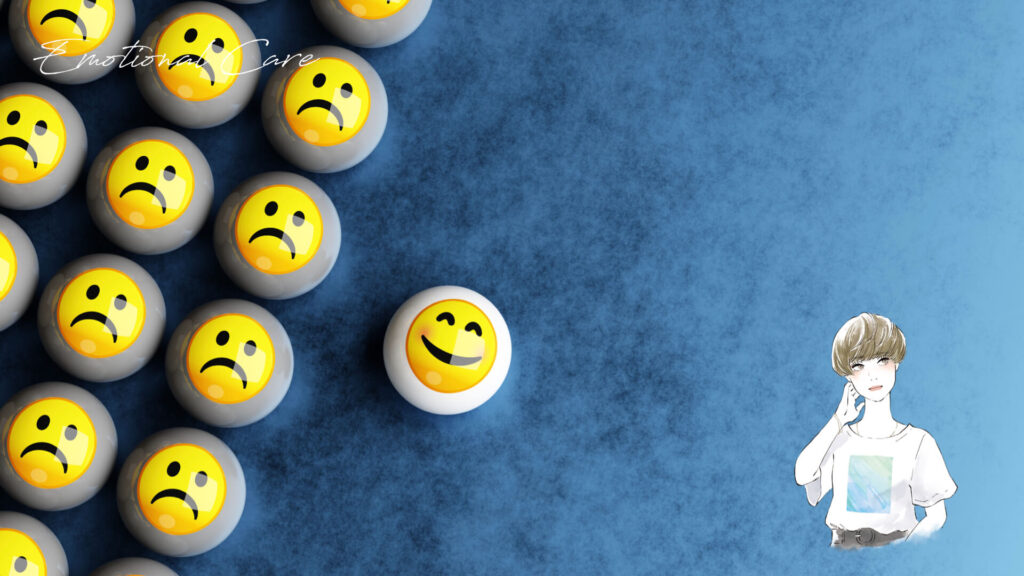
自分の気持ちがわからない──この感覚は、恋愛や結婚、キャリアやお金など、あらゆる悩みの根っこにあります。
表面上は「結婚がうまくいかない」「仕事がしんどい」「将来が見えない」といった具体的な悩みであっても、よくよく掘り下げると「本当の自分の気持ちがわからない」ことが原因になっているケースはとても多いのです。
あなたは何をしているときが幸せですか?
とコーチングで聞かれても答えられない。
今の気持ちはどうですか?
とカウンセリングで尋ねられても分からない。
お見合い相手のことをどう思いますか?
と結婚相談所で聞かれても答えに迷ってしまう。
自分の気持ちがわからないということは、人生における包囲磁石をなくしたようなもの。
方向性が見えないまま進もうとするから、恋愛や仕事、人間関係など、芋づる式に悩みが広がっていきます。
この記事では、そうした「自分の気持ちがわからない」状態について、原因やセルフ診断法、そして解決に向けたステップを総合的に整理しました。
まずは「今のあなたの心の位置」を知るところから始めていきましょう。
Contents
【診断】自分の気持ちがわからないときのセルフチェック
私が運営している脳トレカレッジ(自己対話の学校)では、より良い人生を生きるために 自己対話=自分の気持ちをキャッチして把握する力 を一番大事にしています。
なぜなら「自分の気持ちをどのくらい分かっているか」が、人生の満足度やライフキャリアの方向性に直結しているからです。
実際に相談に来る方の多くは、表面的には「今の人生が嫌」という不満は分かっていても、じゃあ 「自分は何がしたいのか」「どうありたいのか」 が分からない。
ひどい場合は「分かっていないことすら分からない」という八方塞がり状態に陥ってしまっています。
言うなれば、心のアンテナが5Gどころか“圏外”になっているようなもの。
この状態を放置すると、人生の選択すべてがぼやけてしまいます。
そこで、ここでは 「自分の気持ちをどれくらい把握できているか」 を簡単に測れるチェックリストを用意しました。
当てはまる数が多いほど、自己対話が弱まり、自分とのつながりが切れてしまっているサインです。
簡単なYES/NOチェックリスト
まずは「自分の気持ちアンテナ」がどのくらい立っているのかを確認してみましょう。
以下の質問にYES/NOで答えてください。当てはまる数が多いほど、あなたの“心の電波”は弱まっています。
- 「好き/嫌い」を聞かれて即答に迷うことが多い
- 休日に「何をしたいか」がすぐ浮かばない
- 選択の瞬間、まず他人の評価や顔色が気になる
- 「これを選べば正解」と分かっても体が動かない
- 褒められても嬉しさの実感が薄い
- 嫌だったことは語れるが、望みは言語化しづらい
- 感情語彙が少なく「モヤモヤ」「普通」で済ませがち
- モヤモヤが数日以上続くのに、向き合わず先送りしている
判定(YESの数)
- 0~2:接続良好 … 次の「シーン別(恋愛・仕事)」へ進んで具体化を。
- 3~5:接続不安定 …「解決ステップ」の言語化・環境リセットを先に。
- 6~8:接続ほぼ遮断 … まず深呼吸→1分ノートで“今いちばんしてほしいこと”をひらがな一語で書く→そのまま「解決ステップ」へ。
体の反応で分かるサイン
心の声が全くつかめないときは、一旦「体の感覚」に注目してみましょう。
気持ちは見えなくても、体は正直に反応を出してくれるものです。
例えば、ある選択を考えたときに呼吸が深く落ち着くか、それとも浅く乱れてしまうか。
二つの未来で迷っているなら「どちらの方が筋肉がゆるみそうか」「肩の力が抜けそうか」で比べてみるのも一つの方法です。
心に聞いても答えが出ないときは、体に聞いてみる。これはシンプルですが、意外と効果があります。
子どもの例でよくあるのが「学校に行きたくないと熱を出す」「親の気を引きたくて体調を崩す」といった現象です。
心理学の世界でも、本人が自覚できない、あるいは言葉にできない気持ちを体が代弁する──そんなメカニズムが様々な研究や臨床で語られてきました。
つまり、体のサインに耳を澄ませることは、心の奥の声を受け取るための有効な入り口になるのです。
書き出してみるワーク
心の中でモヤモヤしていることも、紙に書き出すだけで整理が進みます。
やり方はシンプルで、日常の出来事や選択肢に「好き/嫌い」「やりたい/やりたくない」の○×をつけるだけ。
たとえば「今の仕事」「週末の予定」「一緒にいる人」「今日のランチ」など、思いついたテーマをどんどん並べて○×をつけてみましょう。
直感でつけるだけで、心の中のぼんやりした気持ちに輪郭が現れはじめます。
もし○×すらつけられずに「?」や「△」ばかりになるなら、それも大切なサインです。
自分はこんなにも自分の気持ちを分かっていなかったんだ…
と視覚的に認識するだけで、自己対話の第一歩が始まります。
【恋愛】彼のことが好きかわからない
ご相談を10年以上受けてきましたが、その中でも「自分の気持ちがわからない」という悩みが最も多く表れるのは、やはり恋愛の場面です。
学校や仕事のように「やらなければならないもの」ではなく、恋愛は感情そのものが羅針盤。
だからこそ、自分の気持ちが見えなくなると、進めることも終わらせることもできず、立ち止まってしまいます。
恋愛で「気持ちが分からない」典型パターン
自分の気持ちがわからなくなったとき、恋愛では次のような状態に陥りやすいです。
あなた自身も当てはまるものがあるかもしれません。
- 相手のことを思い浮かべても「好きか嫌いか」がピンとこない
- 会いたいのか距離をとりたいのか、自分でも判断できない
- 一緒にいるのに「楽しい/安心」といった感覚がぼやけている
- 将来を考えようとしても、頭が真っ白になってしまう
ここで言う「気持ちがわからない」というのは、なんとなく自分の気持ちを察していながら認めたくない──そういう自己欺瞞とは少し違います。
もっと感覚的に不明瞭で、輪郭のない“無感覚”のような状態を指しています。
【仕事】やりたいこと・転職の気持ちがわからない
恋愛と同じく、仕事も「自分の気持ちがわからない」場面がとても多いテーマです。
ただし恋愛と比較すると、仕事は気持ちがわからなくても業務を遂行すること自体は可能です。
上司や同僚に合わせてタスクをこなせば評価も得られるし、収入を得ることもできます。
そのため「気持ちがわからない」ことがすぐに大きな支障になるわけではありません。
しかし、起きている時間の大半を過ごす職場で自分の気持ちを見失っていると、仕事をこなしているのに満足感がなく、「生きている実感」そのものが少しずつ薄れてしまいます。
これが、仕事における“自分の気持ちがわからない”状態の一番のリスクだと言えるでしょう。
仕事で「気持ちがわからない」典型パターン
では、自分の気持ちがわからなくなったとき、仕事ではどんな状態に陥りやすいでしょうか?
- 成果や評価は得られているのに、心の満足感が薄い
- 収入や条件は悪くないのに、やりがいを感じない
- 辞めたいわけでもないのに「このまま続けていいのか」判断できない
- 自分がこれからどんなキャリアを築いていきたいのかが分からず、立ち往生してしまう
仕事の場合、「自分の気持ちを絶対に明確にしなければならない」というよりも、仕事という領域でどれくらい気持ちを重視したいのか、自分の人生の中で仕事をどの程度の優先度で扱いたいのか──そのスタンスを決めることの方が大切です。
仕事に生きがいを求めるのか、生活の安定のために割り切るのか。
この位置づけが定まらないと、どんな選択をしても「本当にこれでいいのかな」と迷いが消えなくなってしまいます。
【人間関係・人生】家族や将来に対して気持ちが見えないとき
恋愛や仕事と同じように、人間関係や人生の大きな選択でも「自分の気持ちがわからない」という状態は頻繁に起こります。
特に家族や夫婦のように距離が近い相手、あるいは結婚・出産・転居といった将来の選択では、気持ちが曖昧になりやすいのが特徴です。
ここでは、人間関係や人生において「気持ちが見えなくなる」典型パターンを整理します。
人間関係・人生で「気持ちがわからない」典型パターン
- 「嫌いじゃないけど好きかどうか分からない」と感じる家族・夫婦関係
- 相手を大切に思っているのに、距離感や関わり方が決められない
- 結婚・出産・転居など、大きな選択ほど自分の気持ちが曖昧になる
- 将来像を描こうとすると、頭が真っ白になり答えが出ない
【心理学的原因】なぜ自分の気持ちがわからなくなるのか?
「自分の気持ちがわからない」と悩む人には大きく2つのパターンがあります。
ひとつは、昔はもっと素直に気持ちを感じられていたのに、環境や経験を通してだんだん見えなくなってしまったケース。
もうひとつは、今まで浅い感情だけで生きてきたけれど、大人になって“もっと奥がある”と気づいたときに、初めて見えなさを自覚するケースです。
どちらも「本当の気持ちがあるはずなのに届かない」ことが共通していて、それが迷子感の正体です。
では実際に、なぜ「自分の気持ちがわからない」状態が生まれるのでしょうか。
背景にはいくつかの心理的な要因があります。
ここでは代表的な3つ──幼少期からの習慣、トラウマ体験、そして無意識の自己防衛──を整理してみましょう。
幼少期から「気持ちを表現しない」習慣
小さいころから「わがまま言わないの」「泣かないの」と言われ続けてきた人は、自然と“自分の感情を抑える”クセが身についてしまいます。
その結果、本来なら浅瀬にあるはずの「うれしい・悲しい」といったシンプルな気持ちですら、口に出すのが難しくなることがあります。
教育や家庭環境の中で「感情よりも正解を答えること」が重視されると、感情を感じ取る力が鈍っていってしまうのです。
こうした「家庭の影響で感情を抑え込むクセが強くなる」ケースは、アダルトチルドレンの特徴とも一部重なります。
より詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
トラウマや拒絶体験
「大好き」と伝えたのに笑われた、「やりたい」と言ったのに否定された──そんな経験を何度もすると、心の奥にある大きな気持ちにアクセスするのが怖くなります。
本音を出す=傷つく、と脳が学習してしまうと、無意識のうちに自分の気持ちを避けるクセが強化されてしまうのです。
結果として「気持ちがわからない」というより、「気持ちを感じないようにしている」状態に陥りやすくなります。
無意識に「本音を見ない」選択
心の奥では気づいているのに、「本音を知ったら行動を変えなきゃいけない」と感じると、人はあえて“気づかないフリ”をすることがあります。
たとえば「仕事を辞めたい」とうっすら感じているのに、生活や人間関係を崩したくなくて、自分でその気持ちを封印してしまう。
深層では分かっているのに、あえて見えないことにする──これも「自分の気持ちがわからない」状態の典型です。
また、無意識に本音を見ないようにしている状態が長く続くと、「出したいのに出せない」というより、“そもそも出す自分がわからない” という状態になります。
詳しくはこちらの記事でも解説しています。
【解決法】自分の気持ちを取り戻す3つの方法
「自分の気持ちを取り戻す」と言っても、一石二鳥の魔法のような方法があるわけではありません。
これまで見てきたように、気持ちが分からなくなる背景には、幼少期からの習慣・トラウマ・無意識の防衛など、長い時間をかけて積み重なった要因があります。
だからこそ、一度に100%すべてを理解できるわけではなく、少しずつ感度を取り戻していく必要があるのです。
そのためにおすすめしたい基本の方法を、ここでは3つ紹介します。
書く・話すことで言語化する
言語化は「気持ちを輪郭のあるものにする」作業です。
ノートに書く、信頼できる人に話す──方法はどちらでも構いません。
大切なのは、もやもやと形のないものに言葉を与え、「これはこういう気持ちなんだ」と認識できるようにすることです。
私が運営している自己対話の学校「脳トレカレッジ」でも、7教科の中の「国語」はこの言語化を柱にしています。(※詳細プログラムは順次公開予定です)
書いても話してもいい、まずは試みること自体が“自分の気持ちを取り戻す一歩”になるのです。
環境を変えて頭をリセットする
自分の気持ちがわからなくなるとき、実は「気持ちがない」のではなく、気持ち以外の雑音に頭の容量を奪われていることが多いです。
世間的な常識、親や大切な人から言われた言葉、メディアで見たノウハウ──こうした外からの声が頭を埋め尽くし、自分の本音が聞こえにくくなってしまうのです。
だからこそ、自分の気持ちに集中できる環境をあえてつくることが有効です。
自然に触れる、芝生に寝転ぶ、山に登るなどのシンプルな方法でもいいし、瞑想や合宿形式のプログラムに参加するのもひとつ。
また、スポーツや運動に没頭することもおすすめです。
体を動かしている間は頭で過去の言葉を反芻する余裕がなくなり、自然と雑音が消えていきます。
安心できる人間関係で感情を出す
もうひとつ大切なのは、安心できる相手の前で感情をそのまま出すことです。
親友や信頼できる知人がいるなら、その人に話を聞いてもらうだけで気持ちが整理されることがあります。
もし身近にそういう存在がいなくても、カウンセラーやセラピストは「心理的に安全な場」を提供しながら、自然と感情を表に出せるようサポートしてくれる専門家です。
この人の前なら大丈夫。
と思える環境で思いきり気持ちを出すことは、心の健康を保つうえでとても効果的です。
【病気との違い】うつやHSPとの関係
「自分の気持ちがわからない」という状態には、いくつかの背景があります。
気質や性格による一時的な迷い、防衛反応としての感情の遮断、うつや適応障害などの医学的な症状、あるいは心理学で言う“成長のプロセス”としての暗闇。
どれに当てはまるかは人によって異なり、外からも、そして本人ですらも判断は簡単ではありません。
ただ一つ避けたいのは、本来は治療や支援が必要なのに「自分で何とかしなきゃ」と抱え込んで、かえって苦しみを長引かせてしまうことです。
もし「数週間~数か月にわたって感情が動かない」「日常生活に支障が出ている」といった状態があるなら、医療や専門家のサポートを検討してください。
その一方で、すべてを「病気」と決めつける必要もありません。
気質の特徴や、人生の節目に起こる“成長の痛み”の一部として現れている場合もあるからです。
大切なのは「病気だからダメ」「気質だから放っておいていい」という二択ではなく、どちらの可能性も視野に入れながら、自分に合ったサポートを受け取ること。
それが「自分の気持ちを取り戻す」第一歩につながります。
【予防策】「自分の気持ちがわからない」に振り回されないために
ここまで、自分の気持ちがわからなくなる原因や、具体的なシチュエーションについてご紹介してきました。
ただ本当は、「自分の気持ちがわからない」という状態にならないことが一番です。
あるいは、すでにその状態になっているとしても、これ以上さらに気持ちを見失わないようにしておくことが大切です。
そのための予防策を、最後に3つご紹介します。
1.日常で小さな感情に気づく習慣を持つ
大きな気持ちがわからなくなるときでも、日常の中には「おいしい」「疲れた」「うれしい」といった小さな感情が必ずあります。
こうした小さな気持ちに意識を向ける習慣を持つと、自分の心とのつながりが切れにくくなります。
2.感情とつながる習慣を持つ
「感情を表現する手段を続ける」というより、まずは“感情とつながる習慣”を持つことが大切です。
ものづくりや音楽、ダンスなど、感情や感性に触れなければ上達できない趣味を持つと、自然と感情にアクセスする回路が開きやすくなります。
「感情とつながる」ことを目的にするのではなく、趣味を楽しむための副産物として感情を使う──このスタンスが結果的に感情の感度を高めてくれます。
3.感情の流れを取り戻せる環境に身を置く
感情のつながりは“慣れ”のようなものです。
水道管や神経回路のように、一度詰まっても再び流れる道筋を作れば回復します。
そのためには、自分ひとりで努力するよりも「感情が解放されている場」に入ってみるのが有効です。
大勢が音楽に合わせて踊る夏フェス、声を合わせる合唱、感情を安全に分かち合うワークショップなど──感情のエネルギーが満ちた空間にいると、自分の中の回路も自然と刺激され、流れが戻ってきます。
まとめ|「自分の気持ちがわからない」は心の成長のサイン
自分の気持ちがわからなくなるのは、心が壊れてしまったサインではなく、むしろ新しい段階に進もうとしているサインでもあります。
「わからない」と感じるのは、それだけ自分の内側に注意を向け始めている証拠です。
すぐに明確な答えが出なくても構いません。小さな気持ちを拾いながら、自分なりの方法で少しずつ向き合っていくことで、本音や願いが自然と輪郭を持ちはじめます。
「どうせわからない」と切り捨てるのではなく、「わからなさ」をきっかけに、心とつながり直すプロセスを大切にしていきましょう。
📝次に読みたいオススメ記事
①「自分探し」の本当の意味とは?──“見つける”より、“思い出す”ための旅
②自分の性格がわからない──診断も占いもピンとこないあなたへ