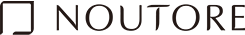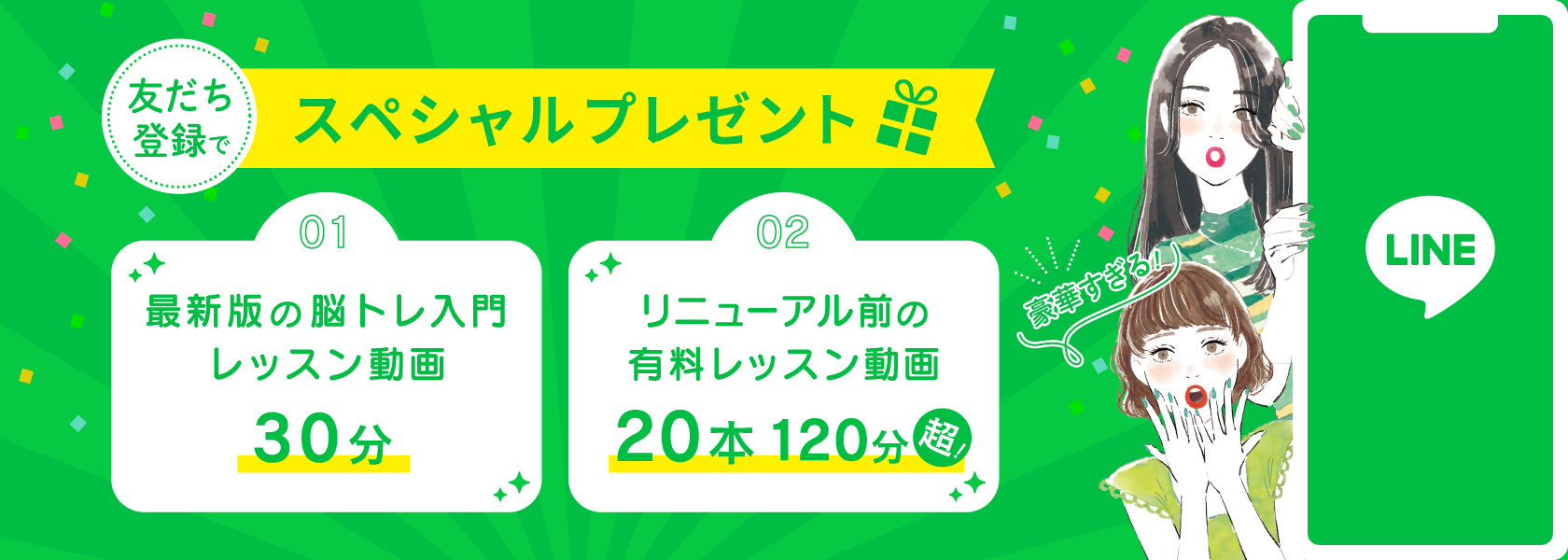幸せとは何か――。
これは古代から現代まで、人類が繰り返し問い続けてきたテーマです。
結婚や成功、お金や健康といった“条件”を満たしても、心から満たされない人がいる一方で、特別な出来事がなくても静かな満足感の中で暮らしている人もいます。
では、幸せを分けるものは何なのでしょうか。
この記事では、哲学・心理学・幸福学の視点を整理しながら、「幸せとは?」の定義を紐解いていきます。
Contents
幸せとは?まず結論から
結論から言えば、幸せとは 「不足感がない状態」 です。
私はこれまで10年以上にわたり女性の人生相談を受けてきましたが、その現場でも強く感じてきたのはこの点でした。
結婚や子ども、経済的な安定といった“とても幸せだと思うだろう”条件が揃っていても「幸せではない」と悩む方がいる一方で、特別な出来事がなくても満足感を抱いている方もいるのです。
人は「足りないもの」に意識を向けやすく、不満や不幸な出来事の方を強調して受け取りがちです。
だからこそ、不足が少なく心が穏やかでいられる状態こそが、安定した幸福に近いといえるのです。
哲学や心理学で語られてきた「幸せ」
幸せの定義は、時代や学問分野によってさまざまに語られてきました。
ここでは代表的な考え方を3つ取り上げます。
哲学的な視点から心理学的な研究までを見ていくことで、幸せの本質に多角的に触れることができます。
アリストテレスのエウダイモニア(よく生きること)
古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、「人間の最高善はエウダイモニアである」と説きました。
エウダイモニアは直訳すると「よく生きること」「人間らしい生の完成」といった意味で、単なる一時的な快楽や喜びではなく、「徳に従った生き方」を通して得られる持続的な充足感を指します。
ここで重要なのは、幸せを「結果」ではなく「生き方そのもの」に見出している点です。
人間が本来もつ理性や徳を十分に発揮し、社会の中で役割を果たしていくことが、最終的に幸福につながるとされました。
マズローの欲求5段階と自己実現
20世紀の心理学者アブラハム・マズローは、人間の欲求を5段階で説明しました。
- 生理的欲求(衣食住など生きるための欲求)
- 安全の欲求(身の安全・経済的安定など)
- 社会的欲求(人とのつながり・愛情)
- 承認の欲求(他者から認められること)
- 自己実現の欲求(自分の能力や可能性を発揮すること)
マズローによれば、下位の欲求がある程度満たされると、より高次の欲求を求めるようになります。
そして最上位に位置づけられる「自己実現」が、人間にとって最も充足感の高い状態=幸せに直結するのです。
つまり幸せは、段階を踏んで成長する中で到達する「自分らしさの開花」といえるでしょう。
各段階ごとにどんな不足感が生まれやすいのか、そしてどう解消できるのかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
22 心が満たされない理由と「マズローの欲求5段階別」解消法
現代心理学における幸福研究(ポジティブ心理学など)
近年注目されているのが、ポジティブ心理学を中心とした「幸福研究」です。
これは従来の「病気や問題をどう治すか」ではなく、「人がより幸せに生きるための条件は何か」を探る学問です。
代表的な心理学者マーティン・セリグマンは、人間の幸福を以下の5要素で説明しました(PERMAモデル):
- P(Positive Emotion) ポジティブな感情
- E(Engagement) 没頭・フロー体験
- R(Relationships) 人間関係・つながり
- M(Meaning) 人生の意味・目的
- A(Achievement) 達成感
このように現代心理学では、「感情」「関係性」「意味」「成長」といった複合的な要素を組み合わせて、幸せを多面的に理解しようとしています。
前野隆司さんの「4つの幸せ」
哲学や心理学のさまざまな研究を見てきましたが、現代の日本における幸福学の第一人者である 前野隆司さん(武蔵野大学ウェルビーイング学部 学部長・教授/慶應義塾大学 名誉教授) は、幸せをよりわかりやすく整理するために「4つの因子」を提唱しています。
この「4つの幸せ」は、日本人の幸福度調査や心理学的な研究をもとに導き出されたもので、学術的な裏付けがありながらも、日常生活にすぐ応用できるシンプルさを持っています。
具体的には次の4つです。
① 自己実現と成長(夢や目標に向かって挑戦する、成長を実感する)
② つながりと感謝(人との信頼関係や感謝の気持ちを大切にする)
③ 前向きと楽観(希望や笑顔、前向きな気持ちを持つ)
④ 独立と自分らしさ(自律・自由・自分らしい選択をする)
これらはそれぞれが独立しているのではなく、互いに影響し合いながら全体の幸福感を形づくっています。
たとえば、挑戦(①)が人とのつながり(②)を深め、そこから感謝や笑顔(③)が生まれ、自分らしさ(④)もより確かなものになっていく、といった循環です。
シンプルに言えば、「幸せ」とはこの4つの因子がバランスよく働いている状態。
だからこそ、「今の自分にはどの因子が不足しているか?」を振り返ることが、幸せに近づくための第一歩になります。
1.自己実現と成長
「やりがいを感じながら成長している」と実感できることは、人間にとって大きな幸福の源です。
新しいことに挑戦したり、スキルを磨いたり、夢や目標に少しずつ近づいている感覚は、自己効力感を高め、心を前向きにします。
大きな成果や目標達成だけが成長ではありません。
- 新しい本を一冊読み切った
- 苦手だった料理が上手にできた
- 職場でひとつ新しい役割を担えた
こうした小さな積み重ねも「昨日より今日の自分が一歩前に進んだ」と思える瞬間です。
日常におけるこうした前進感が、人生全体の満足度をじわじわ底上げしていきます。
その点では、仲間との交流やコミュニティも大きな助けになります。
たとえば私が運営する脳トレカレッジのメンバー限定SNSでは、参加者が「今日は自分の感情を言葉にできた」「小さなチャレンジをやり切れた」といった日々の報告をシェアしています。
“幸せに直結する一撃必殺の出来事”ではない、一見ささやかな体験でも、それを言葉にして共有することで自己効力感が高まり、確かな成長として自覚できるのです。
あなたも、自分だけの“小さな一歩”を日々記録してみてください。振り返ったときに、自分がどれだけ進んでいるかに驚くはずです。
29 理想の自分は未来の自分 | なりたい私になる13の質問
2.つながりと感謝
人との関係性は幸福度に直結する大切な因子です。
家族や友人、同僚との温かいつながり、感謝を伝え合える関係は、孤独感を和らげ、心に安心をもたらします。
心理学や幸福研究では「感謝を表現すること」そのものが幸福度を上げるとされています。
誰かに「ありがとう」と伝えるとき、相手だけでなく自分の心も穏やかになり、安心感が増していきます。
つまり「つながり」と「感謝」は切り離せないペアであり、互いを強化し合う存在です。
また、研究でも社会的なつながりを持つ人ほどストレス耐性が高く、長寿であることが示されています。
人と関わることは、ただ楽しいだけでなく、心身の健康や人生の安定に直結する「見えない資産でもあるのです。
3.前向きな感情
笑顔や楽観的な気持ち、希望を持てることも幸福を大きく左右します。
なんとかなる!大丈夫!
困難があってもそう思える楽観性は、ネガティブな出来事に振り回されにくくし、回復力(レジリエンス)を高めます。
一日の中で小さな喜びを見つけ、感情をプラスに切り替える習慣が、幸せの持続に役立ちます。
ただし、ここで注意したいのは「ネガティブな感情を無理に押し込めて、ポジティブで塗り替えようとすること」は逆効果になりやすい点です。
本当は悲しいのに笑顔を作る、本当は怒っているのに「世界に感謝」と言い聞かせる──こうした“前向き信者”の姿勢は、むしろ心をこじらせる原因になります。
脳トレカレッジ(自己対話の学校)では、前向きな感情は「自然にあふれてくるもの」として捉えます。
ネガティブを抑圧するのではなく、自分の本音を丁寧に受け止め、そのうえで少しずつ物の見方や環境を整える。
すると「ありがたいな」「楽しいな」と感じる瞬間が、無理なく心から生まれてくるのです。
4.独立と自由
「自分で選んで生きている」という実感は、幸せを強く支える要素です。
誰かに強制された生き方ではなく、自分の価値観や判断をもとに選択できる自由――それは規模の大小に関わらず、人に深い満足感をもたらします。
たとえば仕事のスタイルや日々の暮らし方など、自分の意志で選べる領域が広がるほど、人生への納得感は高まります。
近年は「独立と自由」を求める声が一層強まっており、一つの企業に長く勤めるのが当たり前だった時代から、フリーランスや副業、複数の働き方を組み合わせるスタイルへとシフトしつつあります。
SNSやオンラインツールの普及によって、個人が自分の力で仕事を見つけ、世界とつながれる環境が整ったことも大きな後押しとなっています。
こうした時代的な流れの中で
独立したい!自由に生きたい!
という願いは、もはや一部の特別な人だけでなく、多くの人が共通して抱くものになりました。
つまり「自分の意志で選ぶ」という体感は、幸福感を高めるだけでなく、現代社会における普遍的な希望とも言えるのです。
25 人の目が気になるあなたへ。周りを気にせず自由に生きる方法。
幸せには「状態」と「感情」の2つの軸がある
ここまで、哲学者たちの考えや、現代の幸福学者・前野隆司さんが提唱する「4つの幸せ」をご紹介してきました。
これらは幸せを多角的に理解するうえで重要な視点ですが、もうひとつ押さえておきたい整理の仕方があります。
それは「幸せを大きく 状態(ウェルビーイング)と感情(ハピネス) の2つの軸で捉える」という考え方です。
この視点を持つことで、「一時的な幸せ」と「持続的に続いていく幸せ」の違いが、より明確になります。
状態としての幸せ──ウェルビーイング
ウェルビーイング(well-being)は、安定的に「満たされている状態」を指します。
たとえば健康であること、経済的に困っていないこと、安心できる人間関係や環境にあること。
こうした要素が揃うと、人生全体に穏やかで持続的な満足感が生まれます。
一過性の喜びとは違い、毎日の基盤を支える“土台”のような役割を果たすのが、このウェルビーイングです。
感情としての幸せ──ハピネス
一方、ハピネス(happiness)は「嬉しい」「楽しい」といった感情の高まりを伴う、一時的な幸福を指します。
たとえば合格通知を受け取ったとき、大切な人と結婚できたとき、欲しかったものを手に入れたとき
瞬間的な喜びは大きなエネルギーになりますが、時間が経てば落ち着いていく性質があります。
2つの軸を意識することの意味
この2つの軸を区別して考えると、幸せについての見方が整理されます。
「一時的な喜び(ハピネス)がなくても、自分の生活基盤(ウェルビーイング)が整っていれば満ち足りた気持ちでいられる」し、逆に「どれだけ大きな喜びがあっても、基盤となる状態が不安定なら、すぐに不満や不安が顔を出してしまう」のです。
つまり、持続的な幸せを考えるうえでは、この2つをバランスよく満たす視点が欠かせないのです。
「幸せとは?」いちごショートケーキの完成版である
私は10年以上、女性の人生相談を伺ってきて、幸せを考えるときにいつも浮かぶ比喩があります。
それは「幸せはいちごショートケーキの完成版である」というものです。
多くの人は「結婚すれば幸せ」「独立して自由に働けば幸せ」「宝くじが当たれば幸せ」など、人生の“イチゴ”を追いかけます。
確かにそれは一時的な高揚感を与えてくれるでしょう。
けれども、土台となるスポンジがスカスカのままでは、それは“ただのイチゴ”であって、ケーキとしての満足感は続きません。
一方で、スポンジ(土台)がしっかりしていれば、イチゴが多少高級でなくてもケーキとして十分においしく味わえる。
最高級のイチゴをのせても、スポンジが不味ければケーキ全体が台無しになるのと同じです。
私が相談現場で見てきたのも、まさにこの構造です。
多くの人は「イチゴさえ手に入れば」と思い込むけれど、実際に幸せを支えているのは、派手な出来事よりも「日常の土台が安定しているかどうか」なのです。
まず整えるべきはスポンジ=ウェルビーイング
幸せをショートケーキにたとえるなら、スポンジはウェルビーイング(安定した満たされ感)、イチゴはハピネス(一時的な喜び)です。
どちらも大切ですが、順番でいえば まずはスポンジを整えることが最優先。
ウェルビーイングを支える要素は、健康、経済、人間関係、環境などさまざまですが、その中でも特に大きいのが「繋がり」です。
ただし、ここで言う繋がりは「他人との繋がり」だけではありません。
パートナーや家族、友人と繋がることも大切ですが、一番の核になるのは“自分自身との繋がり”です。
現代はSNSやマッチングアプリ、行政のコミュニティ支援など、外との繋がりを広げる仕組みが充実しています。
それでも孤独感や精神疾患が増えているのは、内なる繋がり=自分との関係が切れてしまっているからではないでしょうか。
良い小麦粉でスポンジを焼くように、まずは「自分との繋がり」という質の高い土台を作ること。
その上で外との関係や環境を整えていけば、イチゴがのって初めてショートケーキとして完成します。
この順番を意識することが、遠回りに見えて実は幸せへの最短ルートだと私は考えています。
自分とのつながりを取り戻す「自己対話」
ここまで見てきたように、幸せの根本には「不足感の少なさ」「状態としての安定(ウェルビーイング)」「つながり」という要素があります。
そして、それらを芋づる式に整えていく最初の一歩が、自己対話=自分とのつながりを取り戻すことです。
自己対話を深めることで、まず自分の感情や声に耳を傾けられるようになります。
すると自然に他人とも鎧を着ずにつながれるようになり、孤独感が減っていきます。
結果としてウェルビーイングの土台が整い、そこに「イチゴ=ハピネス」の体験を積み重ねられる。
こうして最終的には「ウェルビーイングとハピネスが両立した幸せの完成版」に近づいていくのです。
まとめ|自分とのつながりが幸せの土台
「幸せとは何か」に、ひとつの正解はありません。
哲学や心理学の研究、現代の幸福学、そして現場での実感を重ねても、答えは人それぞれに形を変えていきます。
ただ確かに言えるのは、大きな不足感が少ないこと、そして自分自身とつながっていられることが、幸せの土台を支えるということです。
その土台が整えば、外とのつながりも自然に育ち、ハピネスの“いちご”も心から味わえるようになります。
幸せを探す旅は、外の世界にだけ答えを求めるのではなく、自分の内側と向き合うことから始まります。
私と“わたし”との再会こそ、それぞれの幸せを形づくる第一歩になるのです。
📝次に読みたいオススメ記事
①充実した生活とは?|外側と内側から考える“満たされた人生”のつくり方
②「楽しく生きる!」最高に満足な毎日を作る秘訣とは?