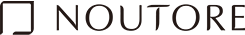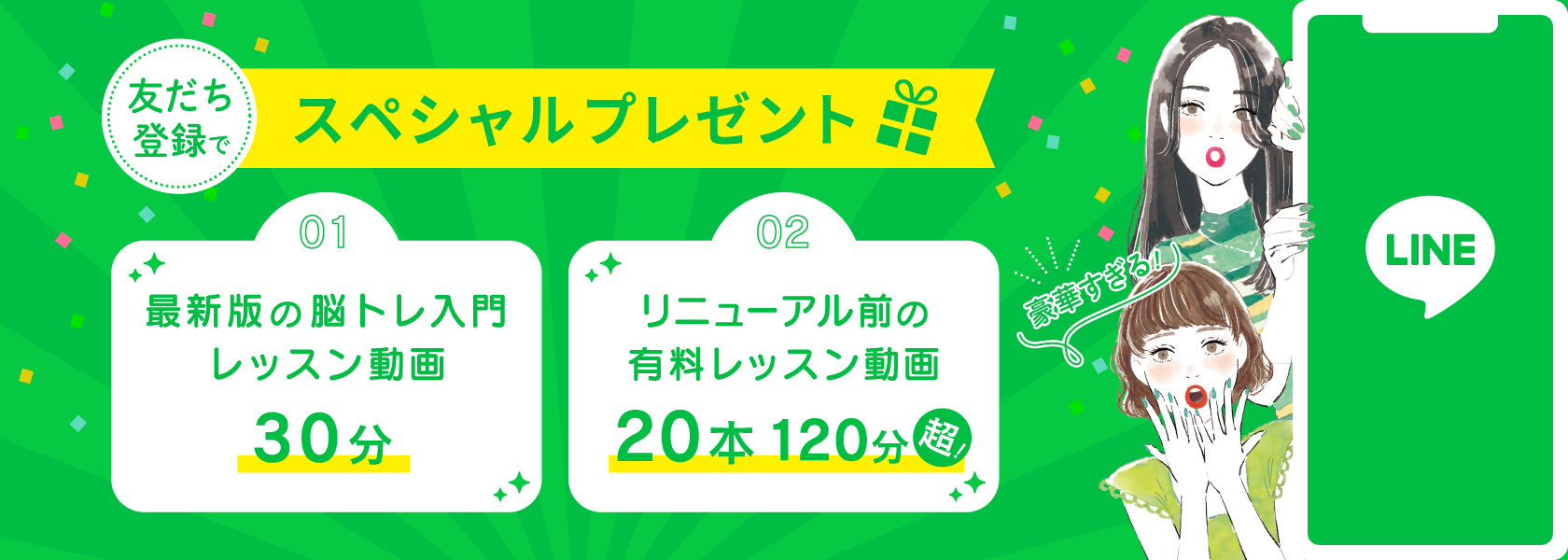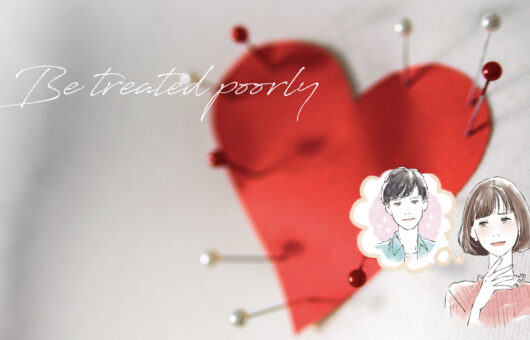相手の立場になって考えなさい。
子どもの頃から耳にしてきた人も多いでしょう。
けれど実際にやってみると、相手と自分は違う存在だからこそ、簡単ではありません。
結局のところ想像にすぎず、本当に意味があるのかと疑問に思う場面もあるのではないでしょうか。
Contents
相手の立場になって考えることに意味はあるのか?
「相手の立場になって考えなさい」という言葉は、学校や家庭、職場、さらには恋愛や友人関係など、日常のあらゆる場面で使われています。
自分が言われる側になることもあれば、相手に投げかける側になることもあるでしょう。
しかし実際に相手の立場に立って考えることは、決して単純ではありません。
同じ状況に立ったとしても、相手と自分の感じ方は異なるからです。
自分ならこう思うと想像して行動した結果が、相手には不快に映ったり、関係をこじらせたりすることもあります。
実際、私の運営する脳トレカレッジ(自己対話の学校)でも、相手の立場になって考えることができない人との関係で悩む人が後を立ちません。
このように、よく使われる言葉でありながら、その実効性に疑問を抱いた経験がある人も少なくないはずです。
では、それでもなぜ「相手の立場になって考える」ことが重要だと言われ続けるのでしょうか。
言い換え・類語に触れてみる
そもそも「相手の立場になって考える」という表現は、状況によってさまざまなニュアンスを持ちます。
言葉を変えてみると、同じ行為でも少し違う角度から見えてきます。
たとえば、以下のような言い換えがあります。
- 思いやりを持つ
- 相手の気持ちを想像する
- 共感する/置き換えて考える
言葉の切り口を変えることで、「相手の立場に立つ」という行為がより多層的に理解できるはずです。
単なる道徳的な指導としてではなく、人間関係を築くうえでのスキル、あるいは成長のための訓練として位置づけられるでしょう。
相手の立場になって考えることと発達段階の関係性
ここまで、「相手の立場になって考える」という言葉がなぜ繰り返し語られてきたのか、その背景について整理してきました。
結論から言えば、この行為は単なるマナーや道徳の強要ではなく、人の発達段階をスムーズに進めるための有効なトレーニングでもあるのです。
人の精神的な成長を表す枠組みのひとつに、「依存 → 自立 → 相互依存」 というプロセスがあります。
これはスティーブン・R・コヴィーの『7つの習慣』でも取り上げられ、ビジョン心理学など多くの心理学的アプローチでも言及されてきました。
この流れの中で「相手の立場を考える」という行為は、それぞれの段階に応じて異なる意味を持ちます。
依存の段階ではほとんど意識できないことも、自立に入るとトレーニングとして大きな効果を発揮し、やがて相互依存においては共同創造の基盤となります。
つまり「相手の立場になって考える」とは、ただ人から好かれるためのスキルではなく、自分自身の発達を後押しする効率的な方法でもあるのです。
この視点を持てば、日常の人間関係の中でこの言葉に出会ったとき、その意義をより積極的に受け止められるようになるでしょう。
発達すると何が得られるのか
では、そもそも自分の精神性を発達させると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
実は依存から自立、そして相互依存へと進むたびに、単に「人間的に成長する」以上の実益があります。
- 依存 → 自立では、自分の願いを叶える力が強まり、主体的に選べる自由度が増す
- 自立 → 相互依存では、他者と協力して大きな成果を生み出す力、社会的影響力が広がる
- 相互依存の定着では、自分のビジョンを形にしながら、他者や社会に貢献できる土台が整う
こうしたメリットを理解しておくと、「発達」という言葉が単なる理想論ではなく、現実の人生に直結する力であることが腑に落ちやすくなります。
依存段階における「相手の立場になって考える」意味と効果
依存は、人の成長におけるスタート地点です。
赤ちゃんが親に完全に依存して生き延びるように、誰しもまずは「誰かに支えてもらうこと」を前提に人生を始めます。
大人になっても、新しい環境に入った直後や、まだ役割を十分に果たせない立場では、精神的に依存的な状態にとどまることがあります。
この段階で繰り返し言われるのが「相手の立場になって考えなさい」というフレーズです。
ただし、それは単なる道徳的なお説教ではなく、依存の段階を抜け出して自立へと向かうための重要なトレーニングでもあるのです。
依存段階の特徴
この段階では、主語が常に「私」であり、自分の欲求や感情を中心に世界を見ています。
赤ちゃんが親に完全に依存するように、精神的な成長のスタート地点では相手の立場を想像する余裕がほとんどありません。
社会的な場面でも同じで、新卒1年目や転職直後など、まだ力を持たない立場では「会社に養ってもらっている」状態にあり、どうしても依存的になります。
なぜ「相手の立場になって考えなさい」と言われるのか
依存段階では、誰かに支えられて初めて自分の生活や立場が成り立ちます。
だからこそ「相手の立場を考える」というのは、単なるマナーや礼儀ではなく、依存段階にある人が周囲と健全な関係を築くための必須条件です。
例えば新卒社員であれば、自分のニーズだけを主張するのではなく
会社全体の中で自分は何を求められているのか
と視点を持つことが、次のステージ=自立へと進むためのトレーニングになるのです。
自立段階における「相手の立場になって考える」意味と効果
依存を抜けて「自分の足で立つ」ことを選んだとき、人は自立の段階に入ります。
ここでは自分の責任で物事を決められるようになる反面、自分の正しさに固執しやすく、相手を置き去りにしてしまうことも少なくありません。
このフェーズで「相手の立場を考える」という行為は、自分中心の視点を緩め、他者を想像するためのトレーニングになります。
まだ未熟さを抱えながらも、自立を確かなものにしていくための重要な練習です。
自立段階の特徴
自立の段階では、自分の力で選び、動けることが中心になります。
責任感や主体性が育つ一方で
自分はこう思う!
自分ならこうする!
という視点に偏りやすく、他者の意見や感情に耳を傾けるのが難しくなることがあります。
なぜ自立の段階でも「相手の立場を考えなさい」と言われるのか
自立の段階に入ると、職場ではリーダーや管理職の立場に立つことも増えてきます。
責任を果たし成果を出す一方で、依存的な人を見下したり、感情を軽視してしまう傾向が生まれがちです。
その結果、仕事はできても「人間的に距離を置かれる」ような摩擦が増えてしまうことがあります。
だからこそ、この時期に「相手の立場を考える」ことを繰り返すのは重要です。
相手が依存の段階にいたとしても、その感情や視野を想像して受け止めようとする。
そうした姿勢を磨くことで、リーダーとしての資質が高まり、次の「相互依存」への橋渡しとなっていきます。
相互依存段階における「相手の立場を考える」意味と効果
自立を十分に育んだ先に現れるのが「相互依存」の段階です。
ここでは自分の責任や主体性を手放すのではなく、むしろ確立した自立を土台に、他者と協働し、共に創り出す関係性が始まります。
このフェーズに入ると、「相手の立場を考える」ことは単なる想像やトレーニングではなく、違いを尊重し合いながら共同創造を進める実践そのものになります。
相互依存段階の特徴
相互依存の段階では、相手の意見や感情を尊重しながらも、自分の意見を押し殺すことはありません。
違いが前提にあるからこそ、互いの強みや視点を組み合わせて新しい可能性を生み出すことができます。
なぜ相互依存の段階では「相手の立場を考える」が共同創造になるのか
この段階での「相手の立場を考える」は、相手に合わせるためではなく、違いをつなぎ合わせて未来をつくるためのものです。
結果として、個人では到達できない成果や喜びを分かち合えるようになり、パートナーシップや社会的な影響力も大きく広がっていきます。
トレーニングとしての“相手の立場になって考える”効果
「相手の立場になって考える」という言葉は、どうしても道徳的なニュアンスで捉えられがちです。
けれど実はそれ以上に、心の成長を進めるトレーニングとして大きな意味を持っています。
心が成熟していくと、できることの範囲が広がります。たとえば体の発達を考えると、まだ歩けない赤ちゃん、ハイハイができる赤ちゃん、歩けるようになった子どもでは、行動できる範囲や見える景色がまったく違います。
同じように心にも成長のステップがあり、段階を重ねるほど「叶えられる願いの規模」が大きくなっていきます。
つまり、心の成長が浅い段階では難しかったことも、成熟していけば自然と可能になっていく。
そのプロセスを支えるトレーニングのひとつが「相手の立場になって考える」なのです。
各フェーズごとに異なる効果や効能を発揮するため、取り組むほどに心のステップが進み、人生の可能性も広がっていきます。
まとめ|道徳ではなく発達の扉
今回取り上げた「相手の立場になって考える」というフレーズは、日常生活のあらゆる場面で耳にするごく身近な概念でした。
けれど、ただの道徳的スローガンとしてではなく、心の発達段階を進めるトレーニングとして捉えてみると、その意味合いは大きく変わってきます。
つい「相手のためにどうするか」という発想に偏りがちですが、実はそれ以上に「自分の成長プロセスを加速させるための実践」として取り組むと、効果は何倍にも広がります。
自分の段階を一歩進めることを目的として、相手の立場を考えることに挑戦してみてはいかがでしょうか。