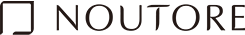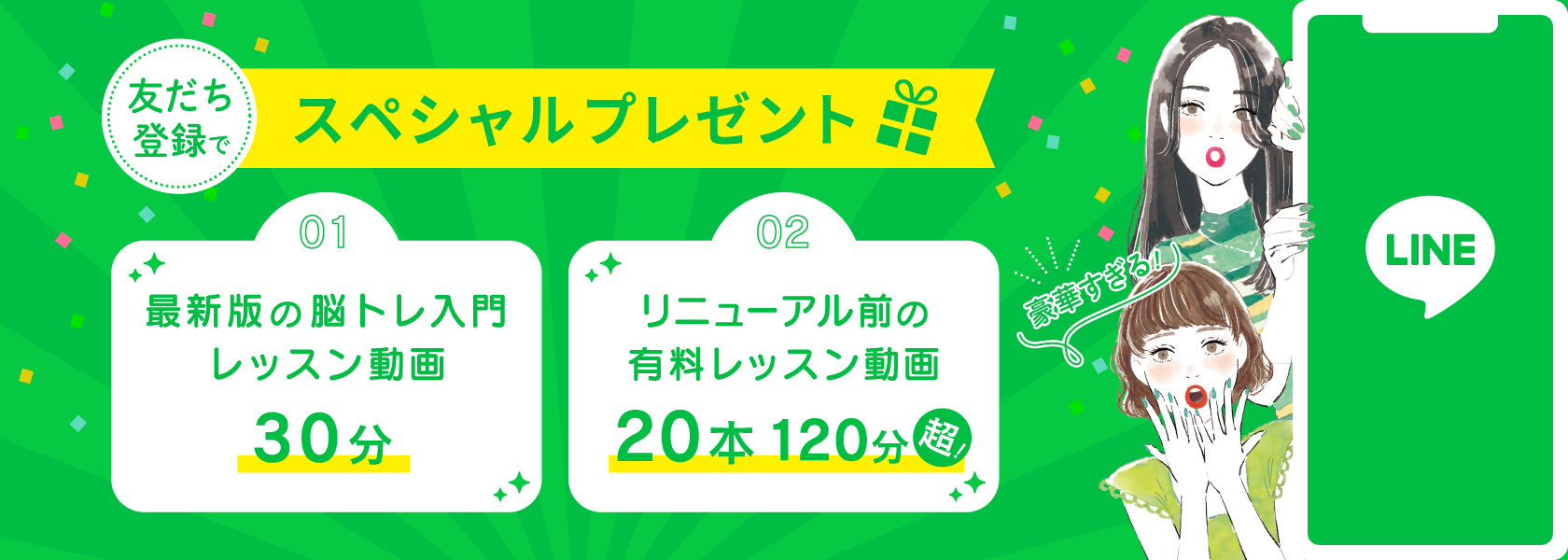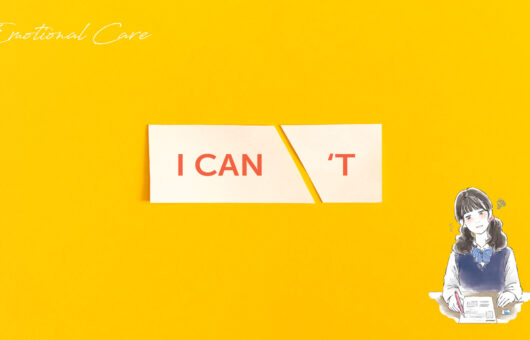私、もしかしてアダルトチルドレンかもしれない
そんなふうに感じたことはありませんか?
恋愛や人間関係でうまくいかないとき、ふと自分の“生きづらさ”に気づく瞬間があります。
その原因のひとつとして、最近よく耳にするのがこの「アダルトチルドレン(AC)」という言葉。
でも、いざ調べてみると定義があいまいで
結局、自分はアダルトチルドレンなの?それとも違うの?
とモヤモヤしてしまう方も多いのではないでしょうか。
今回は、そんな“わかったようでわからない”アダルトチルドレンについて、やさしく丁寧に紐解いていきます。
Contents
アダルトチルドレンとは?──まずはその定義から理解しよう
「アダルトチルドレン(Adult Children)」という言葉は、もともとアルコール依存症の家庭で育った人々を指す心理学用語として使われ始めました。
しかし今では、広く「機能不全家庭(emotionally dysfunctional family)」で育ち、大人になってもその影響を引きずっている人たちのことを指すようになっています。
たとえば、
- 親からの愛情が得られなかった
- 過度な期待を背負わされていた
- 家庭内で安心感を得られなかった
こうした体験が、知らず知らずのうちに“生き方のクセ”として大人になっても残っている。
それが「アダルトチルドレン」の本質です。
心の傾向としては、自己否定、感情の抑圧、過剰適応、他者への過剰な配慮、などが挙げられます。
実は誰もが持っている「満たされなかった記憶」──アダルトチルドレン的な傾向はグラデーション
ここまで読んで、「あれ?私当てはまりそうだなぁ…というか、誰にでも当てはまるのでは?」と感じた方もいるかもしれません。
その感覚、正しいです。
というのも──完璧な親も、完璧な家庭も、この世には存在しません。
どんなに愛情深い親でも、どんなに豊かな家庭でも、「もっと甘えたかった」「もっとわかってほしかった」という思いがゼロの人なんて、いないんじゃないでしょうか。
親との相性、育った時代背景、親自身のトラウマ……そういったものが複雑に影響して、誰の心にも“少しずつ満たされなかった部分”が存在しているんです。
だから私は、アダルトチルドレン的な傾向というのは、「ある/ない」で白黒つけるものではなくて、「どのくらい強く出ているか」というグラデーションでとらえるのが自然だと思っています。
そして、もしあなたが「自分にもそういう傾向があるかもな」と思ったとしたら──
もしかすると、あなたの大切な人も、同じように、何かしら“子どものころの痛み”を抱えているのかもしれません。
アダルトチルドレン的な心のクセは、「特別な人にだけある」ものではなく、誰の中にも、程度の差こそあれ、ひっそりと根づいているもの。
だからこそ、自分のクセに気づいて、優しく扱うことができるようになると、相手の“そういう部分”にも、少しだけ優しくなれるかもしれません。
そっか、みんな家庭でいろいろあったんだよね
そっそうだよね、小さな頃の私たちって、ちょっとずつ不器用で、でも一生懸命だったよね
そんなふうに、あなたのまなざしが、少しだけ柔らかくなること。
それが、たったひとつの“やさしさの連鎖”を生んでいくのかもしれません。
あなたはどのタイプ?アダルトチルドレンに多い6つのパターン
ではここからは、アダルトチルドレンに多く見られる6つの代表的なパターンについてご紹介します。
「え、これ私かも…!」と感じるタイプがあるかもしれません。
もちろん完全に当てはまる必要はありませんし、いくつかのタイプが混ざっている方も多いです。
あくまで“傾向”として、自分を知るヒントにしてみてくださいね。
①ヒーロータイプ|期待に応えようと頑張りすぎる優等生
- ちゃんとしていないと、価値がない
- 完璧でいなければ、見捨てられる
──そんな信念を、無意識に抱えているタイプです。
子ども時代、親から過剰な期待をかけられ、常に「できる子」として振る舞うことを求められてきた人に多く見られます。
親の顔色を読み、成績や習い事で成果を出し、「頑張ること=愛されること」と思い込んで育ってきた背景があります。
そのため、大人になってからも“結果”や“他者からの評価”に自分の価値をゆだねがちです。 たとえば、少しでも失敗すると「自分はダメだ」と感じたり、常に何かに挑戦していないと不安になったり──。
人から見れば“優秀でしっかり者”でも、内側では深い孤独やプレッシャーを抱えていることが多いのが特徴です。
②ロストワンタイプ|目立たず、静かに、存在を消す
- 私はいてもいなくても同じ
- どうせ誰もわかってくれない
──そんな諦めにも似た感情を抱えてきたタイプです。
家庭内で緊張や混乱があるとき、目立たず静かにすることで“嵐をやり過ごす”戦略を身につけた人に多く、感情や欲求を押し殺し、「気配を消す」ように生きてきました。
大人になってからも、自己主張が極端に苦手だったり、人との距離感をつかむのが難しかったりします。 自分の考えや気持ちを伝える前に、「言っても無駄」と心のブレーキがかかってしまうのです。
周囲からは「大人しい人」「ミステリアス」と見られることもありますが、本人の内側では「理解されたいけど、怖い」という葛藤が渦巻いています。
③ピエロタイプ|場を和ませるムードメーカー
家の空気が張り詰めていたとき、冗談や明るさで“場を回す”役割を無意識に担ってきたタイプです。
- 笑わせていれば怒られない
- 楽しいふりをしていれば問題が起きない
──そんな学習から、つらい気持ちを“笑い”で包み隠すクセが根づいています。
そのため、大人になっても「明るくて楽しい人」として振る舞うことが多いのですが、内面には不安や悲しみが蓄積していることが多いのが特徴です。
感情の表現が“笑い”に限定されがちなため、泣くことや本音を語ることに強い抵抗感を持つ人もいます。
「人に気を遣わせたくない」「自分のことは後回しでいい」──そんな健気さがある一方で、心の中に孤独感が広がっていることもあります。
④スケープゴートタイプ|“問題児”として注目を引く
家庭の中で誰かが“悪役”を演じなければならなかったとしたら── その役を、無意識に引き受けてしまったのがこのタイプです。
家庭内に怒りや不満、矛盾が渦巻いていたとき、それを一手に背負うかのように、あえて反抗的な態度を取ったり、問題行動を起こしたりすることで、バランスを取っていた人もいます。
家の中が壊れてしまわないように、自分が“問題”でいればいい
──そんな切実な自己犠牲の形とも言えるかもしれません。
大人になってからも、「どうせ私なんて」「自分は厄介者だ」という自己イメージを抱えてしまいやすく、無意識に人間関係を壊してしまう傾向も。
本当は、誰よりも繊細で、愛に飢えていたからこそ「悪い子」でいることで気づいてほしかった。 そんな“声なきSOS”が、ずっと心の奥で叫び続けているのです。
⑤ケアテイカータイプ|他人の世話で自分の価値を保つ
- 人の役に立っていないと不安
- 誰かの世話をしていないと落ち着かない
──そんな感覚に心当たりがある方は、このタイプかもしれません。
親の機嫌をうかがったり、兄弟姉妹の面倒を見たり、自分よりも“誰か”を優先して生きてきた人に多く見られます。
人の感情に敏感で、空気を読んですばやく動ける優しさを持っている一方で、自分の本音や欲求が後回しになりがちです。
恋愛でも「与えること」が当たり前になってしまい、相手に尽くしすぎたり、依存されたりする関係性に陥ることも。
そして、ふと立ち止まったときに「私の人生って、誰のためのものだったんだろう?」とぽっかり穴があくような空虚感を感じることもあります。
“優しさ”と“自己犠牲”の境目があいまいなこのタイプは、自分自身を満たすことに対して罪悪感を持ってしまうケースも少なくありません。
⑥プラケータータイプ|争いを避け、相手に合わせる
- 波風を立てないように
- 怒らせないように
──そんなふうに常に周囲の空気を敏感に察知して動いてきたタイプです。
家庭の中で、怒りや対立が恐怖だった人ほど、自己主張や感情表現にブレーキがかかりやすくなります。
相手の望むことを先回りして察し、合わせてあげることが“安全”で“愛される方法”だと学んできたのかもしれません。
でもその結果、「自分が何を感じているか」「何を望んでいるか」がわからなくなってしまうことも。
人との関係がうまくいっているように見えても、実は常に“我慢”や“自己否定”のうえに成り立っていた──そんな経験をしてきた方も多いでしょう。
「相手に嫌われないように」ではなく、「私はどうありたいか」を選ぶ感覚を、少しずつ取り戻していくことが、このタイプにとっての癒しの第一歩になります。
タイプが違っても大丈夫。共通する“卒業の3ステップ”
アダルトチルドレン的な傾向というのは、決して“悪いこと”ではありません。
それは、子ども時代に身につけた「生きるための心のクセ」──いわば“体質”のようなものです。
そしてこのクセは、ちょっと不思議な性質を持っています。
たとえば、会社の取引先や、通りすがりの人との関係では、ほとんど顔を出しません。
でも──
恋人、親、パートナー、親友のように、「大切にしたい」「愛されたい」そんな深い関係になったときほど、このクセは浮かび上がってきます。
なぜかというと、それは“親との関係”の中で身についたものだから。
子ども時代、親は私たちにとって「絶対的な愛着の対象」でした。
だから、大人になってからも──「愛したい」「大事にされたい」と願う相手との関係の中で、無意識にその時のクセが再生されてしまうのです。
だからこそ、「自分にはどんなクセがあるか?」を知っておくことは、大切な人との関係を壊さないための、いちばんの予防策になるのです。
ステップ1|自分の傾向を正しく知る
まず最初に大事なのは、「自分の心のクセ」に気づくこと。
それは、自分を責めたり、落ち込むためではありません。
「私はこんなふうに反応しやすいんだな」と、
自分をひとつの“観察対象”のようにやさしく見つめてみることから始まります。
たとえば、
- 期待に応えようと無理してしまう(ヒーロー)
- すぐに気配を消してしまう(ロストワン)
- 笑ってごまかしてしまう(ピエロ)
などなど
あ、これ出てるな
って気づけるだけで、行動の選択肢が広がります。
大事なのは、“ジャッジ”ではなく、“気づき”なんです。
ステップ2|アイデンティティにしないと決める
私はアダルトチルドレンだからしょうがない
──そう思ってしまうと、そこから先に進む力を、自分で封じてしまうことがあります。
でも、本当はこう言い換えていいのです。
私は、AC的な傾向を持っている“時期がある”だけ
それは肩書きでも名刺でもなく、一時的に“そういう心の状態にある”というだけのこと。
私たちはラベルを貼ると安心する生き物です。
でも、ラベルに縛られると苦しくなります。
だからこそ、“自分の本質”と“今ある傾向”を切り離して考えることが、自分を自由にするための視点になります。
ステップ3|“体質”として優しく付き合っていく
アダルトチルドレンの傾向は、何かを“完全に克服”しなきゃいけないものではありません。
それはむしろ、
- 自分がどんな時に反応しやすいか
- どうすれば安心していられるか
そういった“心の取扱説明書”を持つような感覚に近いんです。
たとえば私は、むくみやすい体質なので(笑)
大事な日の前日は水分を控えたり、塩分を減らしたりします。
それと同じで、たとえば
今日ちょっとロストワンっぽいな
って思ったら、人と話す時間を少しだけ長くとってみるとか、
ピエロっぽく笑ってごまかしてるな
と思ったら、そのあと1人でノートに本音を書いてみる──など。
“クセ”を責めるんじゃなくて、“クセ”に気づいて調整する。
それが、自分を育て直していく、ほんとうの意味での「卒業」なのだと思います。
まとめ|あなたの中の“子どもの部分”と仲直りすることから、すべてが始まる
今回ご紹介した6つのタイプ、そして「卒業の3ステップ」。
きっとどこかに、「ああ、わかるな」「ちょっと痛いけど当たってるかも」そんなふうに感じた部分があったのではないでしょうか。
でも、どうか忘れないでいてください。
これらはあなたの“欠点”ではなく、「そうするしかなかった過去のあなたの選択」であり、「そのとき一生懸命に、生き延びた証」でもあるということを。
子ども時代の自分は、今よりずっと小さくて、無力で、環境を選ぶこともできなかった。
でもその中で、精一杯自分を守る方法を見つけて、生きてきた──
それって、本当はすごいことだと思いませんか?
だからこそ、いま大人になったあなたができることは、その“小さな自分”にダメ出しをすることではなく、「よく頑張ってきたね」と、そっと手を差し伸べること。
私たちは、誰の中にも“子どもの部分”を抱えて生きています。
それを否定するのではなく、あたたかく迎え入れるところから、本当の意味で「自分を生きる旅」は始まるのだと思います。
今日のコラムが、その旅の一歩目になりますように。
あなたが、自分のまま、やさしく生きられますように。
📝次に読みたいオススメ記事
①アダルトチルドレンはなぜ恋愛がうまくいかないのか?その原因と心の仕組みを解説
②自分嫌いな人の恋愛傾向|成就したあと苦しくなる理由と対策