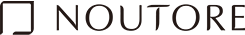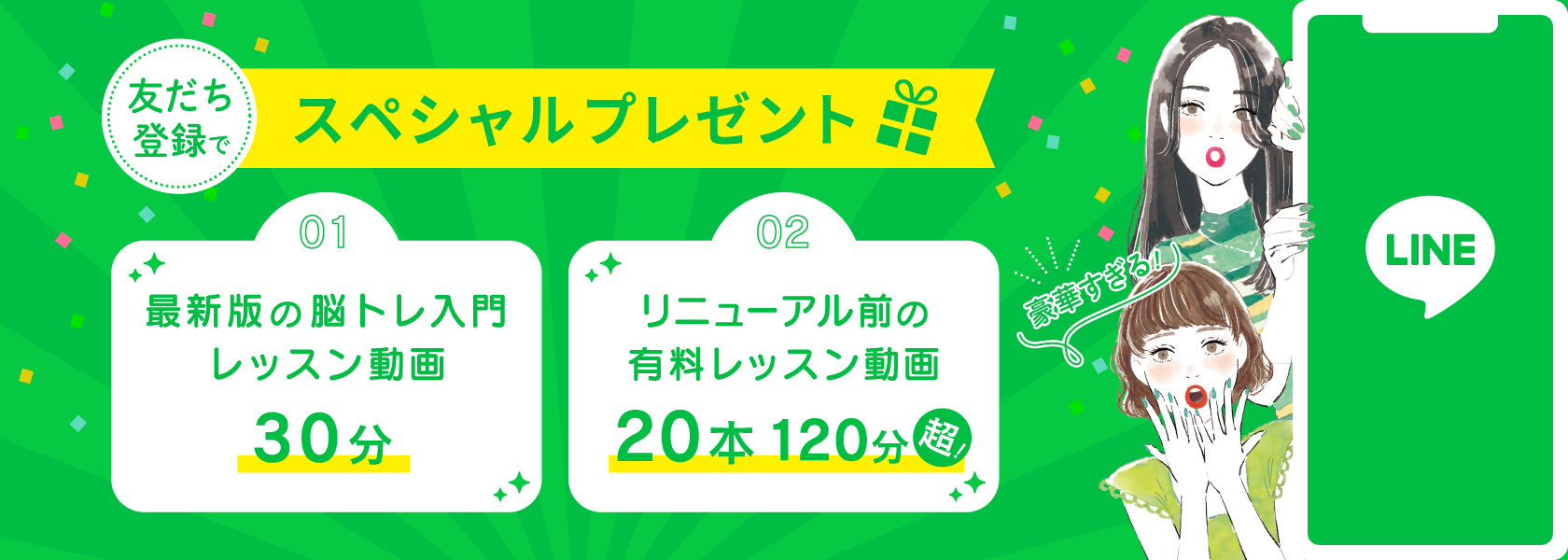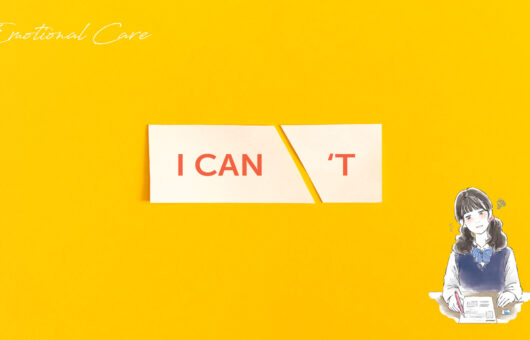理想の自分を描いてみよう──自己啓発やコーチングの場で、こんな言葉を耳にすることは少なくありません。
理想を描き、その姿に向かって努力することが大切
そんなメッセージが広く流通しています。
けれども、ここで立ち止まって考えてみたいのです。
私たちは本当に、自分の「理想の姿」をわかっているのでしょうか?
あたかもスタートラインに「理想像がすでにある」ことを前提にして、多くのメソッドは展開されています。
ところが現実には
自分の理想がそもそもわからない
自思い浮かぶ理想が借り物のようでしっくりこない
と感じる人が大多数です。
だからこそ、この記事では単に「理想を描く」だけでなく、理想の自分とは何なのか、どうやって見つけ、どこから借りてきたものと見分けるのかを、意味・例・考え方の切り口から整理していきます。
Contents
理想の自分とは何か
「理想の自分」と聞くと、多くの人は「夢や目標の姿」を思い浮かべます。
たとえば
- もっと稼いでいる私
- 痩せている私
- 結婚して幸せに暮らしている私
そうした像が一般的に語られる理想像です。
けれど、ここで一度立ち止まって考えてみましょう。
理想は本当に、外から貼り付けた未来像だけを指すのでしょうか。
心理学的に見れば、理想とは「自分の中にある要素が未来に伸びた姿」です。
誰かを見て「素敵だな」と感じるとき、それは自分の内側にもその要素があるからこそ反応していると言われます。
つまり理想はゼロから生まれるのではなく、すでに存在している“素の自分”の延長線上にある未来像なのです。
ここを理解すると、「理想がわからない」と感じるのは、自分が何も持っていないからではなく、ただまだ“自分の内側とつながれていない”だけだと気づけます。
理想の自分は外から与えられるものではなく、自分の中からにじみ出てくるもの。
この視点を持つだけで、理想という言葉が少し現実味を帯びてくるのではないでしょうか。
理想の自分の具体例
理想を言葉にしようとすると、多くの人は抽象的になりがちです。
もっと素敵な自分になりたい
幸せな自分になりたい
そうした表現は分かりやすいけれど、漠然としているため、実感を伴いにくいのです。
実際、私が運営している脳トレカレッジ(自己対話の学校)にも、「理想の生活を手に入れたい」「理想の私になりたい」という思いで来てくださる方が多くいます。
そこで
あなたにとって理想の自分ってどんな姿ですか?
と聞くと、返ってくる答えはたいていふわっとしています。
たとえば──
いつも自由を感じられて、いつも満たされている。会社には行っていないかもしれないけど、じゃあフリーランスで働いているかというと分からない。でもとても幸せな感じ。
こんな風に、具体的な働き方や暮らしの形はまだ曖昧で、「幸せそうな雰囲気」だけが理想として語られることが少なくありません。
理想の自分になりたい気持ちは確かにある。
けれど、その理想がまだ具体的な姿として見えていない。
言うならば「桃源郷」のような、実在するかどうかも分からない夢の場所を追いかけている状態なのです。
だからこそ大事なのは、その桃源郷を無理に追いかけるのではなく、理想像を少しずつ具体的にブレイクダウンしていくことです。
次の章では、そのために役立つ「ジャンルごとのヒント」を整理していきます。
1. 仕事・キャリアの例
理想の自分を考えるとき、まず浮かびやすいのが「仕事や働き方」かもしれません。
ここでいくつかのサンプルを挙げてみます。
必ずしもこれが正解というわけではありません。
自分の理想の輪郭をつかむための材料として、「これは近い」「これは違う」と感じながら読んでみてください。
- 電車通勤が苦手なので、会社まで徒歩圏内、もしくは完全リモートで働いている
- 週5日フルタイムではなく、週3日・1日6時間程度の勤務。それでも正社員扱いで安定した待遇を得られている
- 人間的に尊敬できる上司の下で働き、チームの人間関係も良好。人間関係でストレスを抱えることがない
- 会社員ではなくフリーランスとして独立し、収入は会社員時代の3倍に増えている
- 自分が書いたエッセイを有料で購読してくれる読者がいて、朝から晩まで文章を書くだけで生活が成り立っている
こうした「仕事やキャリアの理想像」をサンプルとして眺めてみると、どこか心が動くものがあるはずです。
理想を考える出発点は、“完璧な答え”を出すことではなく、「これならちょっといいかも」と思える感覚に気づくことなのです。
2. 恋愛・結婚の例
次に、恋愛や結婚、パートナーシップの理想について考えてみましょう。
脳トレカレッジ(自己対話の学校)でも、このテーマでご相談いただくことは本当に多いのですが、仕事やキャリアと同じく「理想の関係は?」「理想の相手は?」と聞いても、答えはふわっとしていることが少なくありません。
そこで、もう少し具体的に「理想の自分が手に入れているであろう関係性」をサンプルとして挙げてみます。
- 友達の紹介で自然に出会った彼と、付き合い始めてからは一緒におしゃれなお店を開拓するのが共通の趣味になっている
- 彼は私のことを本当に好きで、毎日欠かさず連絡や愛情表現、デートの誘いがあり、不安になる暇もない
- 婚活で疲弊することなく、自然な流れで将来を見据えた交際に進めている
- 結婚して家族になっても、恋人同士のように毎日を楽しめている
- 子どもが生まれても「パパ」「ママ」ではなく名前で呼び合い、夫婦としての関係を大切にできている
恋愛や結婚の理想は、多くの人にとって「自分の願望を全部詰め込みたくなる領域」です。
そのため、まるで二次元のキャラクターかと疑うくらい完璧な相手像を求めてしまうことも珍しくありません。
ただ、ふわっとしたイメージに留めるよりも、あえて具体化することで「私が欲しいのはこういう空気感なんだ」と気づける瞬間が増えます。
3. 内面・性格の例
では次に、「こんな自分でありたい」という内面や性格面での理想を考えてみましょう。
外側の環境やライフスタイルと違って、内面の理想はどうしても抽象的になりやすいものです。
ここでは、日常の場面に落とし込んだサンプルを挙げてみます。
- 朝起きた瞬間から気分がよく、「今日はどんなふうに楽しく過ごそうかな」と自然に思える
- 友人から頼みごとや悩みを相談されたときに、嫌な気持ちにならず心よく話を聞ける
- 好奇心や探究心を抑え込まず、日常の中で新しい刺激を楽しめている
こんな自分でいられたら、今の私って本当に私らしくて素敵だな
と思えるような理想の自分のサンプルになるものはありましたか?
ただし注意したいのは、自己肯定感や自己受容感が低いときほど「自分ではないもの」を理想に掲げやすいという点です。
4. ライフスタイルや健康の例
最後に、ライフスタイルや健康について「理想の自分」のヒントになりそうなサンプルを見ていきましょう。
体や暮らしの質は、日々の積み重ねがそのまま未来をつくります。
だからこそ、どんな環境で、どんなリズムで生活したいのかを具体的に描くことが大切です。
- 個人オーナーが営む小さなカフェが点在する地域に住み、散歩がてら立ち寄れる
- 大きな窓のある部屋で、東から差し込む朝日とともに目覚まし時計なしで自然に起きられる
- 仕事を終えたらその足でジムに立ち寄り、汗を流してから帰宅するのが当たり前のルーティンになっている
- コンビニ弁当ではなく、近所の産直で買った新鮮な野菜を使って自炊し、満足感のある食事をしている
こうした具体的なイメージを描くと、「自分の体と心が喜ぶライフスタイルはどんなものか」が見えてきます。
理想の生活を誰かのモデルに合わせるのではなく、自分の体調や感覚に合ったリズムを意識することが、本当に続けられる理想につながるのです。
理想の自分がわからないのは普通のこと
「理想の自分がわからない」──そう感じる人は少なくありません。
むしろそれはとても自然なことです。
なぜなら、多くの理想はもともと借り物だからです。
SNSで流れてくる華やかな暮らしや、親や社会から植え付けられた「こうあるべき」という像を、知らず知らずのうちに自分の理想として貼り付けてしまう。
その結果、本当の自分の声とつながっていないからこそ「これが理想なのか分からない」という迷いが生まれるのです。
でも、それは決してマイナスではありません。
借り物の理想に振り回されるよりも、「自分にはまだはっきりした理想がない」と気づいていることの方が、ずっと健全なスタートラインです。
むしろここからが、本当の意味で「自分に合った理想」を探していける出発点になります。
理想の自分と本当の自分の関係
ここまで見てきたように、「理想の自分がわからない」と悩む背景には、そもそも理想と本当の自分の関係が整理されていない、という事情があります。
- 本当の自分=いまここに存在している素の部分
- 強さも弱さも含めて、飾らない「ありのまま」の自分
- 理想の自分=未来に投影した像。いまの自分が「こうありたい」と思う姿
両者は対立しているように見えて、実際には深くつながっています。
健全な理想とは、本当の自分にすでにある要素が未来に伸びていった姿です。
「私は人に優しくありたい」と感じるなら、それはすでにあなたの中に優しさが存在しているからこそ芽生える理想です。
理想が本当の自分の延長線上にあるとき、それは自然に育っていく未来像になります。
一方で、不健全な理想もあります。
それは「本当の自分を否定するために掲げた仮面」のような理想です。
たとえば本当は内向的で一人の時間が好きなのに、「理想は社交的で誰とでもすぐに仲良くなれる自分」と設定してしまうと、努力すればするほど疲弊していきます。
大切なのは、「その理想が自分の素の部分の延長か? それとも素の自分を打ち消すための仮面か?」を見極めることです。
この視点を持つだけで、理想と現実のギャップの苦しさがぐっと軽くなります。
理想の自分になれる人・なれない人・なれても苦しい人
理想の自分を思い描いたとき、それが自分にとってどう作用するかは人によって異なります。
ここでは大きく2つのタイプに分け、その中の一部に特別なケース(C)を整理しました。
自分はどこに当てはまるかを照らし合わせながら読んでみてください。
タイプA:理想の自分に無理なくなれる人
理想が「素の自分の延長」にある場合、自然と理想に近づいていけます。
たとえば、人に優しくしたいという思いがもともと強い人が「もっと周りを笑顔にしたい」と願うなら、その要素はすでに自分の中にあるため、努力も楽しみに変わっていきます。
このタイプにとって理想は、未来の自分を引っ張る力であり、無理のない成長のプロセスになります。
タイプB:理想の自分になるのが難しい人
理想が「借り物」だったり、本来の自分を否定するために掲げられたものだと、どんなに頑張っても自分ごととして根づきません。
たとえば、本当は静かな暮らしを好むのに「理想は社交的で常に人に囲まれている自分」と設定すると、追いかけるほど疲れてしまいます。
この場合に大切なのは、理想に近づけない自分を責めることではなく、「そもそもその理想は本当に自分の声なのか?」を見直すことです。
タイプC:理想の自分になれても苦しい人(Bの一部)
タイプBの中には、理想を現実化する力を持ち、実際に叶えられる人もいます。
しかし、その理想自体が完璧主義や自己否定の延長にあるため、たとえ手に入れても心は満たされません。
「理想の体型を手に入れたのに、まだ足りないと感じてしまう」「理想のキャリアを築いたのに、達成感よりもプレッシャーが増した」──そんな状況に陥りやすいのがこのタイプです。
このように、理想の自分との関わり方には「A=無理なくなれる」「B=難しい」「C=Bの中で叶えられるけど苦しい」という段階があります。
自分がどこにいるかを理解することが、理想との健全な距離感を見つける第一歩です。
理想と現実のギャップに疲れたときの視点
理想と現実のギャップは、必ずしも悪いものではありません。
適度な差は成長の原動力になります。
ただし、あまりに遠すぎる理想は「自分にはないものを追いかけている」という勘違いから生まれることが多く、心をすり減らしてしまいます。
そんなときは、視点を変えてみるのがおすすめです。
- 1年前の自分から今を見たら、すでに成長している点が見えてくる
- 未来の自分から今を見たら、「その努力は確かに実を結んでいる」と感じられる
こうして時間軸をずらして眺めてみると、ギャップは「苦しみ」ではなく「歩みの証」として受け取れるようになります。
理想の自分を探すより「素の自分」を見つめる
ここまで「理想の自分」について見てきましたが、最も大切なのは無理に理想を探すことではありません。
むしろ、調味料を足していない“素の自分”=本体に目を向けることです。
誰かから借りてきた理想を掲げても、途中で疲れてしまいます。
けれど、自分の素の部分にある感覚や価値観を丁寧に見つめると、その延長線上に自然と「未来の理想像」が立ち上がってきます。
理想は掲げるべき目標ではなく、素の自分が育っていった先に現れる姿です。
だから「理想を見つけなきゃ」と焦る必要はありません。
まずは自分の素の部分を知り、その声を聞くことが、最も確かな未来への道しるべになるのです。
本当の自分を見つめるための問い(例)
では先ほどの段落に続いて、「素の自分」に目を向けるための具体的な入り口を用意してみましょう。
細かいチェックリストや大量の質問に答える必要はありません。
むしろ、シンプルで深い問いを数個持っているだけで、自分の輪郭ははっきりしてきます。
ここでは、そのための問いを3つご紹介します。
1. 誰にも見られなくてもやりたいことは?
人に評価されなくても、収入につながらなくても、なぜか続けてしまうことはありますか?
それは、素の自分が自然に求めている行為であり、外側の基準に左右されない「本体の欲求」です。
- 絵を描くこと
- 散歩すること
- 本を読むこと
他人の目を気にせずにやっている行動を思い返すことで、素の自分の核が見えてきます。
2. どんな時に心が落ち着く?
人によって心が安らぐ瞬間は違います。
静かな場所で一人になっている時かもしれないし、信頼できる人と雑談している時かもしれません。
その「落ち着きの場面」を丁寧に思い出すと、自分が本来大事にしたい価値観や、人間関係の距離感が浮かび上がってきます。
3. それを続けた未来にどんな自分が立ち上がる?
上2つで見つけた行動や場面を、数年先まで続けている自分を想像してみてください。
そこに立ち現れるのは、無理やり作った理想ではなく、素の自分が自然に育っていった姿です。
「理想の自分」は遠くに掲げる目標ではなく、この延長線上に立ち上がる未来像だと気づけるはずです。
まとめ|理想は問い続けるプロセス
ここまで「理想の自分」についてさまざまな角度から見てきました。
大切なのは、理想を外から借りてきた像として追いかけるのではなく、素の自分の延長にあるものとして受け止めることです。
理想は「一度見つけて終わり」の答えではありません。
その時々の経験や状況によって形を変えながら、問い続けることで少しずつ育っていくものです。
だから理想の自分は「なれる/なれない」と線を引くものではなく、本来の自分が時間をかけて育っていく姿なのです。
焦って答えを探すのではなく、問い続けながら日々を歩むことが、最も自然に理想の未来へとつながっていきます。
📝次に読みたいオススメ記事
①「自分を出せない」と感じるとき──ほんとは、“出す自分”がわからないだけかもしれない
②「自分探し」の本当の意味とは?──“見つける”より、“思い出す”ための旅