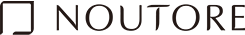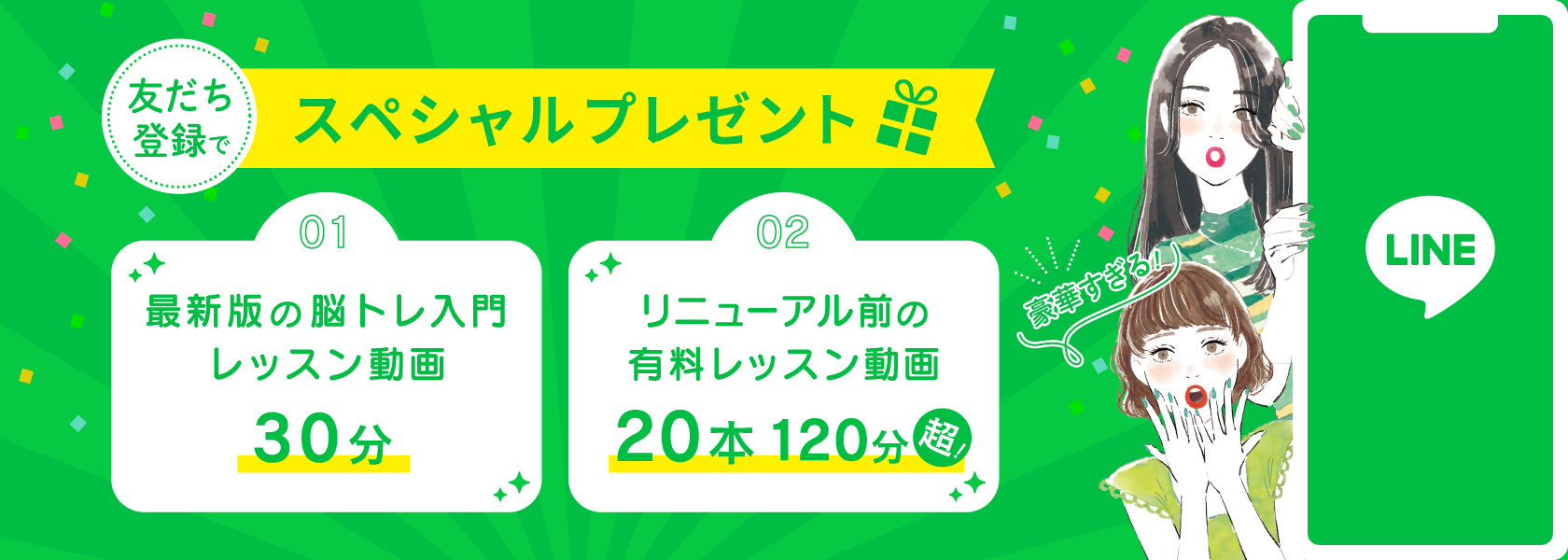彼氏がかまってくれない──
その言葉の裏には、言い切れない不満や、わかってもらえない孤独感が潜んでいます。
恋人との関係は、ただ一緒にいるだけでは成立しません。
言葉や態度、LINEの頻度、会う回数──それらひとつひとつに、「私は大切にされているか?」という問いが無意識に込められています。
けれど、いざ“かまってくれない”という違和感を自覚してしまうと、それが雪だるまのようにふくらんで、次第に苦しさへと変わっていくことがあります。
この記事では、そんな「かまってくれない」という感情の背景にある心理構造をひもときながら、不安や不満に飲み込まれず、関係性を整えていくためのヒントをお届けします。
Contents
構ってほしい=意識を向けて欲しいという願い
もっとかまってほしい──
それは決してワガママではありません。
“あなたを見てるよ”というサインが欲しいという、自然で健全な願いです。
もちろん、頭ではわかっているのです。
- 仕事が忙しいのかもしれない
- 最近は趣味やサークルの時間を大切にしているのかもしれない
- もしかすると、少しずつ私への関心が薄れてきているのかもしれない
でも、事情があるのは理解していても、それでもやっぱり思ってしまうのです。
付き合っているのだから、私にも意識を向けてほしい。
私と一緒にいる時間を、ただの“義務的なもの”ではなく、楽しんで過ごしてほしい。
私という存在を、いまこの瞬間に“ちゃんとここにいるもの”として、感じていてほしい──そう願ってしまう。
それは、物理的に一緒にいるかどうかではなく、“意識”がこちらに向けられているかどうかに、私たちの安心感が直結しているからです。
- そばにいてもスマホばかり見ている
- LINEの返信はどんどん素っ気なくなる
- 一緒にいても、目が合わない。リアクションが薄い
そうした“ほんの小さなズレ”が、「私っていま、ここにいていいのかな?」という不安を静かに膨らませていくのです。
だから、「かまってくれない」と感じるとき、それは単なる寂しさではなく、“あなたの意識”が私に向いていないことへのサイン。
「もっと見てほしい」「ここにいるってわかってほしい」と感じるのは、人と人との関係性を大切に思っている証拠です。
その願いの存在そのものを、まずは否定しないであげてほしいのです。
「彼氏がかまってくれない」不満の奥にある本音
- LINEの返信が遅い
- 会っても楽しそうじゃない
- 忙しいのはわかるけど、なんか寂しい
こうした“かまってくれない”という不満の奥には、実はもっと繊細な願いが眠っています。
ここでは、その願いを5つに分解して見ていきましょう。
本音① 私は愛されてると確信させて(愛の確認)
一番の土台にあるのは、「ちゃんと愛されてるのかどうか不安」という感情です。
人は、愛されているという確信があってこそ、安心して関係に身をゆだねることができます。
でも、彼がそっけなくなったり、会話が減ったり、ふとした瞬間にこちらを見ていなかったりすると──
その確信がふと揺らぎ
私のこと、まだ好きなのかな…?
と不安が顔を出します。
そうなると、頭ではわかっていても、心が追いつかなくなる。
だからこそ、「ちゃんと好きって言って」「私のこと、どう思ってる?」と確かめたくなるのです。
それは、「不安だから重くなる」のではなく、確信が得られない関係ほど、人は確認行動を増やすしかなくなるという自然な構造です。
“構ってほしい”という言葉の裏には、そんな「愛の確証」が欲しいという、切実な想いが潜んでいます。
本音② 私をいつも想ってると安心させて(注目の確認)
たとえ毎日会えなくても、忙しくても、「あなたの中に私はちゃんと存在してる?」と感じられるだけで、不安はずいぶんと軽くなります。
逆に、LINEの返信が遅くなる、既読スルーが続く、会ってもどこか上の空──
そうした些細な“気の抜けた瞬間”が重なると、「もうどうでもよくなってきたのかな」と心がざわついてしまいます。
これは、単なる寂しがり屋の反応ではありません。
人間は、自分という存在が「他者の意識の中にちゃんとある」と実感できてこそ、心の安定が保たれます。
だからこそ、“かまってくれない”という感情の奥には、「私はあなたの中で、今どんな存在なんだろう?」という注目の確認欲求が静かに宿っているのです。
本音③ 私の存在を常に肯定して(存在の肯定)
無視された。ないがしろにされた。気持ちを受け止めてもらえなかった──
そうした小さな否定が積み重なると、やがて「私には価値がないのかもしれない」という自己否定につながってしまうことがあります。
恋愛は、単なる時間の共有ではありません。
相手の意識の中に、自分がどう扱われるか、どう感じ取られているかが、自己肯定感に直結してしまうのです。
だから、「かまってくれない」「無関心にされている」と感じるとき、私たちはただ寂しいのではなく、存在そのものが否定されているような痛みを抱えることになります。
“構ってほしい”という言葉には、
私はここにいていい
私は大切にされている
そう思わせてくれる眼差しを、今この瞬間も向けていてほしいという、強い願いが込められているのです。
本音④ 私の求めに応じて(応答への欲求)
人は、自分の感情や欲求に“反応してもらえる”ことで、関係性の存在を実感します。
「それいいね」と言ってくれる、「大丈夫?」と聞いてくれる。
そういうシンプルな応答の中に、私たちは「この人は、ちゃんと私と向き合ってくれている」という安心を見つけるのです。
でも、構ってもらえない状態が続くと、まるでこちらの発信が宙に浮いたまま、どこにも届いていないような気持ちになってしまう。
「私の求めに応じてほしい」というのは、ただワガママを叶えたいわけではありません。
「ちゃんと対話のキャッチボールが成り立っていると感じたい」という、健全で基本的な関係欲求なのです。
本音⑤ 私を理解して(理解への渇望)
いちばん奥にあるのは、「私の気持ちをほんとうにわかってほしい」という深い渇望です。
相手がこちらの感情に共感してくれないと、「言わなきゃ伝わらないのか…」「話してもどうせわかってもらえない」と感じ、
やがて、伝えること自体をあきらめてしまうようになります。
でもその“あきらめ”の奥には、「理解されたい」という願いが、形を変えてずっと残り続けています。
“構ってほしい”という言葉には、単なる寂しさ以上に、「私は理解されるに値する存在なんだ」と実感したいという、存在の深層にある欲求が込められているのです。
なぜ私たちは「見てほしい」とこんなにも願ってしまうのか
彼氏がかまってくれないの…
この気持ちを誰かに漏らすと、「大人なんだからもう少し落ち着こうよ」「それって重いよ」と、たしなめられることがあります。
自分でもふと、「私はいい大人なのに、こんなことで不満を抱えるなんて…」と、自分を責めてしまうこともあるかもしれません。
でも本当は、「構ってほしい」「見てほしい」という願いは、私たち人間に備わった本能的な仕様なのです。
それは、甘えや未熟さではなく、むしろとても自然な心の動きなのです。
存在の証明は他者を必要とする
もし、地球上に自分しかいなかったとしたら──あなたは、自分が「ここにいる」と確信できるでしょうか?
鏡もなく、他人の姿もない世界。
そこでは、自分という存在すら実感できなくなる。そんな不安が湧いてきませんか?
人は、誰かに声をかけられたり、注目されたり、見られたりすることで、自分の存在を確認するようにできています。
それが文明のない時代であっても、環境が違っても変わらない、人間の根本的な構造です。
だからこそ、誰かに無視されるというのは、ただ話しかけられないという以上に、「存在を無かったことにされる」という感覚を引き起こします。
そして、それがどれほど深いダメージをもたらすか──いじめの代表例が「無視」であることが、その強烈さを物語っています。
つまり、「誰かに見てもらうこと」「注目されること」は、人間にとってただの“欲”ではなく、存在の安定を保つために欠かせない“確認作業”なのです。
自我が薄い子供=他者の眼差しが必要
小さな子どもを思い浮かべてください。
彼らはしょっちゅう
ねえ見て見て!ママ、こっち見て!
と訴えてきます。
それはただの甘えではありません。
子どもは、自我がまだ確立されていないからこそ、「自分が今ここにいる」という感覚を、大人に“観測”してもらうことで確かめようとしているのです。
たとえば、カブトムシを見つけたとき、「見て見て!」と大人に伝えたがるのは、自分が見ているものが確かにこの世界に存在していることを、大人の眼で裏づけてもらいたいからです。
不思議なのは、子どもたちは同じ年頃の子にはあまり「見て見て」と言わないこと。
必ず、大人──この世界で自分より長く存在している“確かな存在”に対して、見てほしいと訴えます。
これはまさに、存在の安定感を“観測者”から得ようとする、本能的な動きなのです。
実際、小さな子どもが、誰もいないはずの空間に向かっておしゃべりをしていたりすることがありますよね。
それを見た大人が、「そんなのいないよ」「そこには誰もいないでしょ」と否定すると、子どもはだんだんそうした“見えない存在”を話さなくなったりします。
自分の見ている世界が、「大人から見たら存在していないものだ」と理解したとき、子どもは「これは存在しない」と判断し、自分の感覚にふたをするのです。
こうした背景を思い返すと、「構ってほしい」「見てほしい」という感情が、子ども時代だけに許されたものではないことがわかります。
むしろ、それは人間という存在の“初期設定”として組み込まれているものであり、大人になっても、その欲求が完全に消えるわけではないのです。
もちろん、大人になるにつれて、他者の眼差しに依存しすぎない力を育てていくことも大切です。
でも、だからといって「見てほしい」という気持ちを抱くこと自体を否定しなくていい。
人間であるかぎり、見てほしい。だからこそ、私たちは関係性の中で生きていく。
この視点に立つことで、自分の“かまってほしい”という気持ちも、少しだけやさしく抱きしめられるかもしれません。
彼氏にかまってもらう3ステップ
それではここから、実際にどう整えていけばいいかを見ていきましょう。
ポイントは、彼の態度を直接変えようとするのではなく、“関係性全体”をゆるやかに整えていくこと。
急がず、順番に、内側から。
ステップ①|「どうして見てくれないの?」のループを止める
最終的に、彼からの注目や愛情をもう一度感じられるようになる──それは十分可能です。
けれど、多くの人がここでつまずいてしまうのは
どうしてもっと見てくれないの?なぜ返信くれないの?
と、“責めるループ”から入ってしまうことです。
このループは、実は逆効果になりやすいです。
彼は責められていると感じ、防御反応として、さらに距離を置こうとする。
その結果、あなたはさらに不安になり、もっと訴えたくなってしまう──そんな悪循環が生まれてしまいます。
だからまずは、「攻める」ことをいったんやめる。
悲しさや寂しさが湧いてくるのは当然ですが、その感情を外にぶつける前に、まずは自分の中にある気持ちに耳を澄ませることから始めてみましょう。
「いったん止めよう。話はそれからだ」
この一呼吸が、次のステップへの扉を開いてくれます。
ステップ②|自分とのつながりを取り戻す
「彼に構ってもらえない」という現実があるとき、それは単なる偶然ではなく、自分の内側との関係が投影されたサインかもしれません。
引き寄せの法則、鏡の法則、潜在意識──
こうした言葉に馴染みがある方なら、きっとピンとくると思います。
私たちは、自分が自分に与えているものしか、外の世界からも受け取れない。
つまり、「彼に構ってもらえない」と感じているとき、あなたの中にいる“内なる子ども”が、大人であるあなたに向かって、「もっと私を見て」と叫んでいる可能性があるのです。
ここで必要なのは、彼をどうにかしようとすることではなく、まずあなた自身が、あなたに構ってあげること。
今、自分ってどんな気持ちだろう?
私は本当は、何を望んでるんだろう?
今日の私が少しでも嬉しくなるには、何をしてあげられるかな?
そんなふうに、自分の気持ちや欲求に少しずつ意識を向ける時間を増やしていく。
その積み重ねが、内側の安定を育てていきます。
ステップ③|彼の態度が自然と変わりはじめる
そして不思議なことに、自分とのつながりが深まってくると、彼の態度が自然と変わっていくという現象が、少しずつ起こり始めます。
あなたの内面が整うことで、雰囲気や言葉遣いが変わる。
それに彼が敏感に反応し、意識があなたに戻ってくる。
別に特別なアプローチやテクニックを使わなくても、関係性全体が「引き合う」状態へと移っていくのです。
これは、「自分が自分に構っている」という安心感や自己肯定感が、にじみ出るから。
だからもう、無理に追いかけて、無理に愛情を引き出そうとしなくても大丈夫です。
自分を整えることが、いちばん遠回りに見えて、いちばん効果的な「かまってもらう方法」だったりするのです。
まとめ|「構ってほしい」は、人として自然な願い
彼氏がかまってくれない──そんなふうに感じるとき、私たちが本当に求めているのは、
ただ一緒にいる時間ではなく、意識を向けてもらうこと、存在を受け止めてもらうことなのかもしれません。
愛されているという確信、想われているという安心、自分の存在が肯定され、反応が返ってきて、理解してもらえること。
それらはすべて、人として生きるうえで欠かせない“心の栄養”です。
それは決して“重たい”願いではありません。
誰もが心の奥に抱えている、とても静かで、でも確かな欲求です。
だからこそ、まずは自分の中にある気持ちにそっと耳を澄まし、「私は今、何を感じている?」と問いかけてみる。
その一歩から、外側の関係性にも少しずつ変化が訪れます。
彼の態度を無理に変えようとせずとも、あなたがあなたに向けるまなざしが、やがて世界をゆるやかに変えていきます。
本当に欲しかった「つながり」は、他者の反応を追いかけることではなく、自分との対話の中から、静かに育っていくのかもしれません。
📝次に読みたいオススメ記事
①彼氏が忙しくて寂しい…イライラの理由と3つの対処法
②彼氏にイライラが止まらない理由とは?恋愛中の感情をコントロールする3ステップ