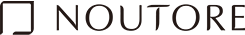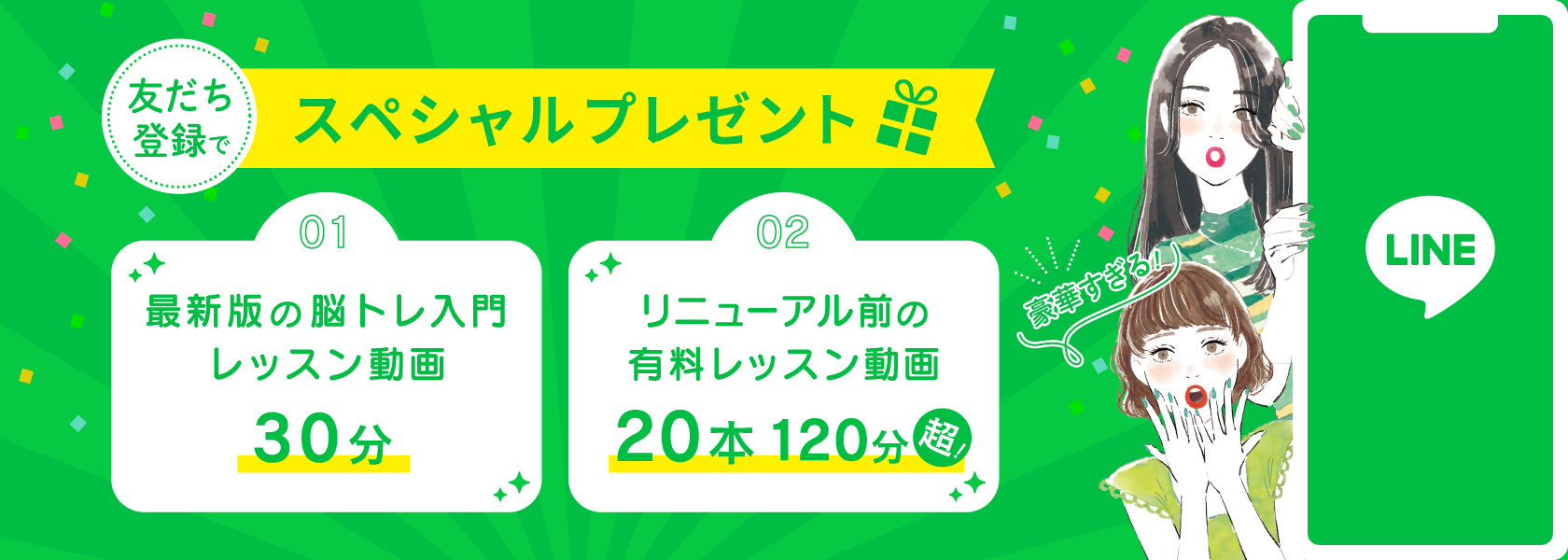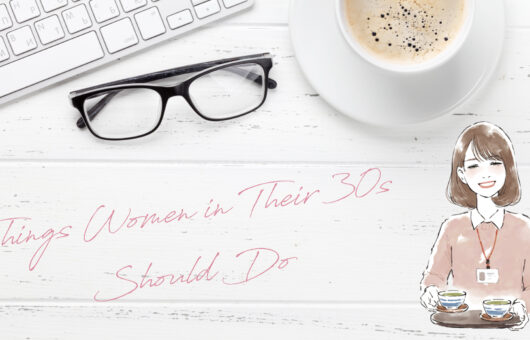やらなきゃいけないのに、どうしてもできない。
頭ではわかっているのに、体が動かない。
やらなきゃ、やらなきゃ…と思えば思うほど、焦りと自己嫌悪だけが膨らんでいく。
どうして私は、こんな簡単なこともできないんだろう
そんなふうに、自分を責め続けてはいませんか?
でも、まず安心してください。
何を隠そう──というより隠してもいませんが、このコラムを書いている私自身も、やらなきゃいけないことがまったくできない人間です。
約束はよく忘れるし、提出物はギリギリ、時間には遅れることも多く、 振り込みでは桁を一桁、時には二桁間違えることもあります。
決して褒められた話ではないのですが、それでも私は、問題なく──というよりは、問題は起きていても、問題なく幸せに生きています。
だから、今「やらなきゃいけないのにできない…」と悩んでいるあなたに、まず伝えたいのです。
それでも、生きていけます。 それでも、大丈夫です。
そして、もし少しだけ余裕があるのなら── 今の「できなさ」を、責めるのではなく整える方向に、一緒に見つめなおしてみませんか?
Contents
やらなきゃいけないことができない人には、2つのタイプがある
「やらなきゃいけないのに、できない」という悩みを抱えている人には、大きく分けて2つのタイプがあります。
どちらが優れているとか、どちらが“より深刻”ということではありません。
ただ、この2つをごちゃ混ぜにして語ってしまうと、対処法がかえってぼやけてしまうのです。
だからまずは、自分がどちらのタイプに近いのか、そっと確認してみてください。
Aタイプ: やらなきゃいけないことの“範囲”が広すぎる人
このタイプの人は、「やらなきゃいけないこと」が山のようにあります。
でも、よくよく見てみると、その中には本当はやらなくてもいいこと、 あるいは自分以外の誰かがやっても問題ないことまで、含まれていることが多いのです。
- 他人が困るかもしれないから、と引き受けた頼まれごと
- 「ちゃんとした人なら、当然やっているはず」という思い込みから入れた家事や習慣
- 自分の限界を超えてまで維持しようとしている人間関係や役割
こういったことが積み重なって、気がつけば「やらなきゃいけないことリスト」が、物理的にも心理的にもパンクしている状態に。
このタイプの人は、朝起きた瞬間から、頭の中に「やらなきゃ」「忘れちゃいけない」「あれも終わってない」がフル回転しています。 まるで、重たいリュックを背負ったまま、毎日山登りをしているような感覚。
でも、よく考えてみてください。
そのリュックの中、本当にあなたが背負わなきゃいけない荷物だけが入っていますか?
Bタイプ: 一般的な“当たり前”がどうしてもできない人
こちらのタイプは、「タスクの多さ」というより、“ひとつひとつの行動”がうまく進まないという感覚に悩んでいます。
- やろうと思っていたのに、気づいたら1日が終わっていた
- 返信をしようとしてスマホを開いたのに、別のアプリを見て終わってしまった
- 手続きをしようと思うたびに、体が重くなって動けない
こうした「うっかり」「気が抜ける」「どうしても気が乗らない」という感覚は、本人にとっては決して甘えではないのです。
場合によっては、エネルギーの枯渇や感覚の過敏さ、発達特性や神経系の影響が関係していることもあります。
また、ここにはもうひとつの可能性があります。
それは、自分の中で“何かが切り替わろうとしている”兆しです。 無意識が、「今まで通りのやり方では、もう進めない」と教えてくれているのかもしれません。
Aタイプ「やらなきゃ」の範囲が広すぎる人へ3つの処方箋
このタイプの人にとって一番つらいのは、 「できない」というより、「終わらない」ことかもしれません。
終わらないのに、次から次へと「やるべきこと」が降ってくる。
それをこなせない自分に、どんどんがっかりして、 「もっとちゃんとしなきゃ」「これくらい普通はできるよね」と、自分に鞭を打ち続けてしまう。
でも、本当に大切なのは、まずこの問いです。
「それ、本当に“私がやらなきゃいけないこと”ですか?」
①やらなきゃいけない“風”のものを仕分けしてみる
“本当に必要なToDo”と“勝手に背負った義務”は、見た目がよく似ています。
でも、内側からの感覚はまったく違います。
- 「頼まれたから」と言って断れなかった用事
- 「完璧にやらなきゃ」と勝手にハードルを上げた家事や仕事
- 「普通はこうするもの」という“べき思考”からくるルール
こうした“やらなきゃいけない風”のものは、心の中の他人の声から生まれていることが多いのです。
優しくあらねば。期待に応えなきゃ。ちゃんとしなきゃ。
それ、本当に“自分の声”でしょうか?
②「手放すこと=さぼり」ではなく「設計の見直し」
本来、“やらなきゃ”が多すぎるのは、その人が怠けているからではありません。
むしろ責任感が強く、まじめで、周りをよく見ている人ほど、この罠に陥りやすいのです。
だからこそ、「削る」「ゆるめる」「やめてみる」ことに対して、罪悪感を感じやすい。
でもそれは、“さぼる”ことではありません。
自分の暮らしや心を、もう一度設計し直すための時間です。
「何をするか」だけじゃなく、 「何をしないか」も、ちゃんと選んでいいのです。
③まずは“削れる1つ”だけ、決めてみる
全部を一気に変えようとしなくて大丈夫です。
まずは、この1つだけは、もうやめてみる──そんな小さなところからでいい。
- 朝イチでメールチェックしない
- 苦手な人への返信を1日遅らせる
- 無理に“いい人”を演じない
Bタイプ「当たり前」がどうしてもできない人への処方箋
このタイプの苦しさは、とても説明しづらいものです。
なぜなら、“見た目には”たいした問題に見えないことだからです。
やろうと思えばできるでしょ?
なんでそんな簡単なこともできないの?
周囲の人にそう言われてしまえば、それ以上、説明のしようがない。
でも、本人にとっては深刻な焦燥感と自己否定の連鎖につながっていることがあります。
①できないのは“意志の弱さ”ではない
「やらなきゃ」と思っても体が動かない。
手続きや連絡といった*“ごく日常的なこと”*が、なぜか進まない。
気づいたら先延ばししていて、自己嫌悪に陥る──。
これらはすべて、意志の問題ではなく、脳の特性や心理的な抵抗反応によって生じている可能性があります。
たとえば:
**ADHD(注意欠如・多動症)**の特性を持つ人は、先延ばしや集中の困難さを抱えやすく、
特に*刺激の少ない作業(事務処理・手続き・メール返信など)*に取りかかれないことが多くあります。
これは“意志が弱い”のではなく、脳内の報酬系がうまく活性化しないことによるものです。
**自閉スペクトラム症(ASD)**傾向がある場合には、急な予定変更や曖昧な指示に対する不安感やパニックが先に立ち、
思考がフリーズしたり、体がストップしてしまうことがあります。
過去のトラウマ体験や過度のストレス経験が、「行動を起こす=危険」「失敗=拒絶される」と無意識に結びついている場合、
たとえ小さなToDoでも、深層心理では“回避すべきもの”として処理されてしまうことがあります。
つまり、「できない」の背景には、
- 脳の機能的特性(ADHD、ASDなど)
- 心の防衛反応(拒否・フリーズ・回避)
- 認知の癖(完璧主義・自己否定・他人基準)
といった構造的な要因があるのです。
②「普通はできること」を、自分に合わせて翻訳しよう
誰かにとって“普通にできること”でも、あなたにとっては気力・集中力・情報処理・感覚刺激すべてが関わる“総力戦”かもしれません。
- 「普通は計画的に動く」は、タイムマネジメント能力に依存
- 「普通はすぐに連絡返す」は、即応ストレスに耐える力に依存
- 「普通は忘れない」は、ワーキングメモリと生活環境の単純さに依存
つまり、“普通”とは環境と特性の偶然の一致で成立しているに過ぎないのです。
自分の特性を否定せず、「できる形に翻訳する」ほうがずっと実用的です。
- 予定は「午前/午後」だけでざっくり把握する
- 返信は「テンプレ保存+習慣化」で感情を使わずに処理する
- 1タスク1時間ではなく、「3分→15分→45分」と段階着火型で着手する
これらは、「できない人の逃げ方」ではなく、**“脳に合った生産性の最適化”**です。
③「気が抜けるとき」は、脳が“守っている”サインかもしれない
やる気が出ないとき、何度も同じところで躓くとき。
それはあなたの中の何かが、「今はまだ行かない方がいい」とブレーキをかけているのかもしれません。
- 体感的にエネルギー残量がない
- そのタスクが「正解」ではないと直感している
- 過去に似た場面で傷ついた記憶がうずいている
脳は常に「自己保存のための判断」をしています。
つまり、“できない”という状態は、何かを守っている証でもあるのです。
だから、「できるようになる」ことを目指す前に、なぜ今の自分はそれを止めているのか?という問いの方が、ずっと大切かもしれません。
「やらなきゃ」に飲み込まれないための3つの視点
「やらなきゃいけないのにできない」と悩んでいるとき、 私たちの心は、知らず知らずのうちに“正しさ”や“責任感”に飲み込まれがちです。
これくらい、普通はできるはず
とにかく早く何とかしないと
できない私はダメだ
そんなふうに、自分をどんどん追い詰めてしまう。
でも、いったん立ち止まって、こう問い直してみてほしいのです。
そもそも、“やらなきゃ”の正体って、何なんだろう?
ここでは、“やらなきゃ”という思い込みに飲まれないための3つの視点をお届けします。
① 本当は「やりたくない」ことではないか?
「やらなきゃいけない」と思っていることの中には、 実は「本当はやりたくない」「心がNOを出している」ことが紛れていることがあります。
でも私たちは、“やりたくない”という感情を持つこと自体に、 罪悪感を覚えるように育ってきました。
- 「やりたくないなんて、わがままじゃないか」
- 「こんな小さなことすら面倒くさがってる私は甘えてる」
- 「感情で動くのはダメだ」
でも、やりたくないにはやりたくない理由があるんです。
過去にその行動で傷ついた経験があったり、 今の自分の価値観とは合っていなかったり、 実は誰かの期待を勝手に引き受けていたり。
だから、「やらなきゃいけないのにできない」と感じたとき、 それは本音が顔を出してくれているタイミングなのかもしれません。
② “できなさ”は才能の兆しかもしれない
できないことには、必ずしも“苦手”という意味だけがあるとは限りません。
むしろ、「今の生き方や枠組みでは、その才能が扱いきれない」という状態の表れであることもあります。
- 言葉に敏感すぎて、メール一通がなかなか書けない人
- 完璧にやりたくなる衝動が強くて、着手するまでに時間がかかる人
- 頭の中にたくさんのアイデアがありすぎて、一つのことに集中できない人
その“できなさ”は、実は精度の高さ・想像力・繊細さ・創造性という資質の裏返しかもしれません。
脳や心が、「まだ外に出す準備が整っていない」と感じて、 その才能を温めている状態だとしたら?
「なんでできないの」と責めるよりも、 「これは何かの前触れかもしれない」と待ってみることも、ひとつの選択肢です。
③ 焦るほど「自分の声」が聞こえなくなる
私たちは焦っているとき、心の内側にある“微細な声”がまったく聞こえなくなります。
- どこから始めればいいかもわからない
- 自分が何を感じているのかさえわからない
- とにかく“何か”を終わらせなければとパニックになる
でも実は、焦っているときほど、 行動よりも“感覚”に戻ることが何よりの特効薬になります。
- 今、自分の体はどんなふうに感じているか
- どの場面で、ふっと気が遠くなるのか
- どんな言葉を聞くと、ホッとするのか
そういう“肌感覚のデータ”を丁寧に拾っていくと、 少しずつ、「いま何をしたいのか」「どんな手順が合っているのか」が見えてきます。
焦る気持ちを否定しなくていい。
でも、焦りだけに乗っ取られないように、立ち止まる時間を持ってみてください。
まとめ|できないときほど、自分の設計図を見直すチャンス
「やらなきゃいけないのにできない」という状態は、 一見、足りなさやダメさの象徴のように見えるかもしれません。
でも実はそれは、古い仕組みがもう合わなくなってきたというサインなのかもしれません。
- 背負いすぎていた役割に、もう体がついていけなくなっている
- 他人の期待に合わせた行動が、自分の本音をすり減らしている
- 社会のテンプレートに無理やりフィットさせていた生き方に、限界が来ている
そんなとき、心や体は「ちょっと待って」とブレーキをかけてきます。 それが、“できなさ”というかたちで現れるのです。
だからこそ、「できるようになること」をゴールにするのではなく、 「なぜ今できないのか」を丁寧に眺めてみてください。
そこにはきっと、今のあなたの設計図を見直すための手がかりが詰まっています。
- どんな状況だと動けなくなるのか
- どんな前提が、自分を無意識に縛っているのか
- 本当は、どうしたかったのか
“できない”という現象の奥には、 あなたの生き方を更新するためのデータが眠っている。
やらなきゃいけないことができない日があってもいい。 すぐに結果が出なくても、何かを手放しても、立ち止まってもいい。
焦るたびに、「あ、今の私は設計図の見直しタイムなんだな」と思い出してもらえたら、 その“できなさ”もまた、意味のあるプロセスになるはずです。
📝次に読みたいオススメ記事
①頑張れないのは甘えじゃない。心のSOSを解読する5つのヒント
②やる気が出ない本当の理由とは?自己対話で人生を整える5つの視点